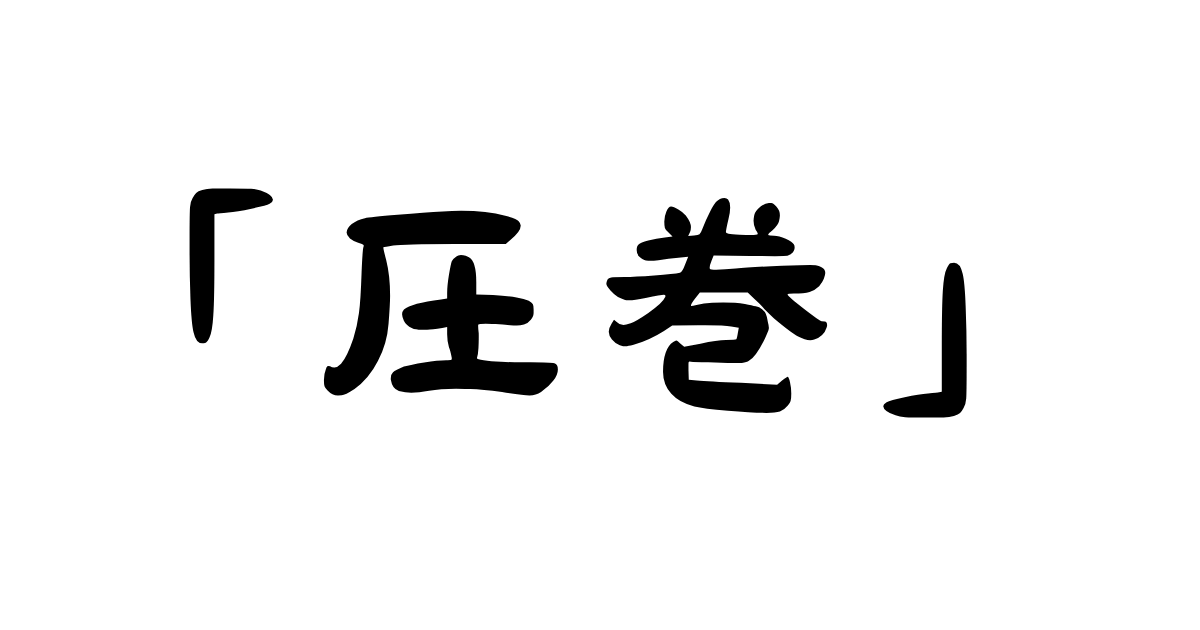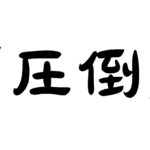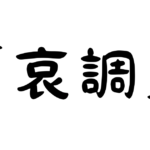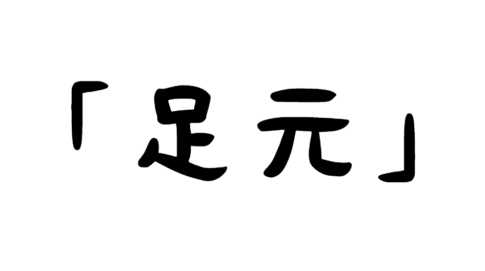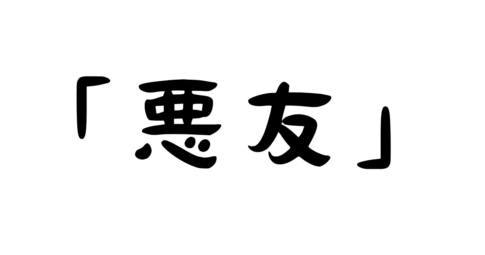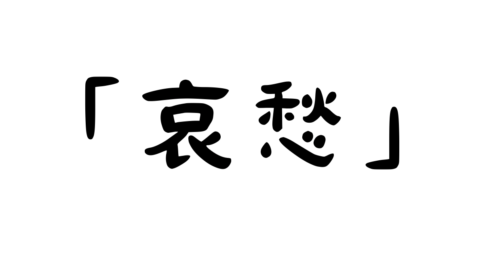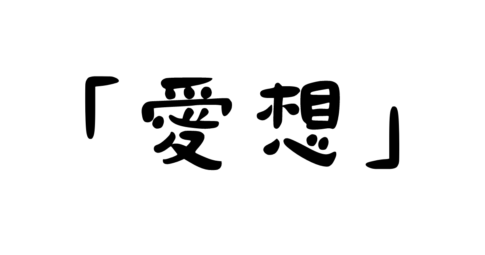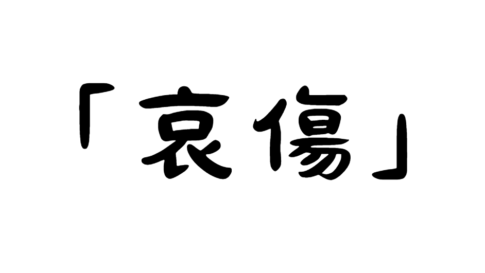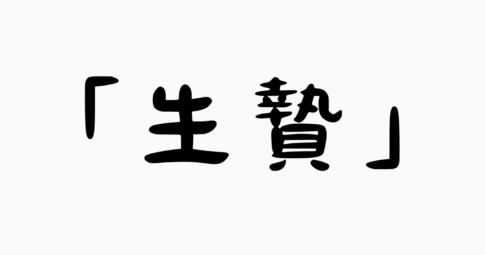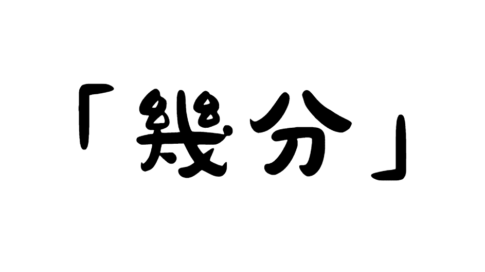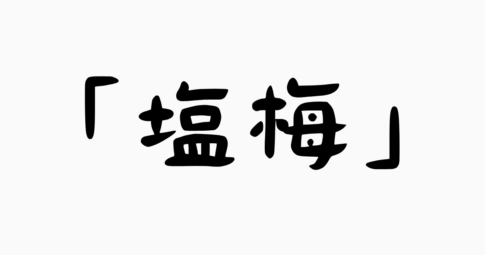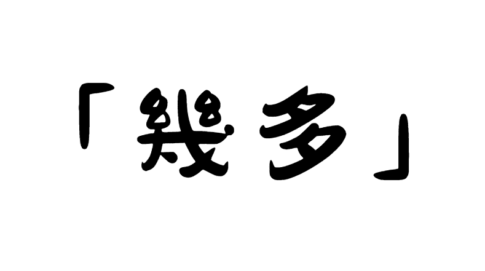「圧巻」とは褒め言葉?
「圧巻(あっかん)」とは、「全体の中で一番優れた部分」「ある特定の分野や領域の中で最も優れていること」を表す褒め言葉です。
単純に「素晴らしい」というニュアンスで使用するのは正しい表現ではありません。「全体の中で最も優れている」ことを褒めるときに使います。
- この映画の圧巻は、なんと言っても最後の戦闘シーンだ。
- 舞台のダンスシーンは圧巻で、誰もが心を奪われる。
- オリンピックで魅せた羽生選手の圧巻の演技は他の追随を許さなかった。
- 今日はいろんなアーティストが登場したが、中でも歌唱力のある彼の歌が圧巻だった。
- 圧巻の夜景でした。
などのように使われます。
5番目の「圧巻の夜景」のように「全体」を示さずに単純に「圧巻」を使う場合は、「これまでにみたことがない」「人生の中でも経験したことがない」という意味を含みます。漠然と「素晴らしい」夜景というのを表す場合には、「圧巻」は適切ではありません。
「圧巻」は故事成語ですが、その由来は中国の科挙と呼ばれる官吏(国家公務員)の登用試験にあります。
「圧巻」の「巻」は試験の「答案用紙」のことを指し、「圧」は用紙の「上において圧力を掛ける」という意味です。
つまり、科挙において試験の答案用紙(巻)を保管する時に、もっとも優れた答案(巻)を一番上に置いた(圧)、という出来事が「圧巻」の由来です。
「圧巻」は元々「書物の中で最も優れた部分。他に抜きん出た詩文」という意味でしたが、転じて「全体の中で最も優れている部分」という意味になり、書物だけに限らず、いろいろな場面で最も優れていることを表す言葉に変わりました。
「圧巻」の類義語として近い意味を持つ表現には、「圧倒」「壮観」「出色(しゅっしょく)」などがあり、「見どころ」「ハイライト」「山場」なども言い換えに使われます。
また、「圧巻」は「作品の中の最もすぐれたところ」という意味なので、対義語は「作品の中で特にすぐれていない」「優れたところがない」ということになります。
「伯仲(はくちゅう)」「互角(ごかく)」「月並(つきなみ)」などが対義語としてあります。
ところで、「圧巻」は故事成語ですが、「科挙圧巻」という四字熟語もあります。
先述した通り「科挙」というのは中国における難関の官吏登用試験ですから、「科挙圧巻」は「試験で最もすぐれた成績を出すこと」の意味があります。
「圧巻」の使い方




「圧巻」の例文
- ・・・だけど、重盛諫言の場は平家物語の中の圧巻でありましてね、文章もなかなかいいんです。
- ・・・この本は、すべての章に味があるが、「二日酔」の項目は圧巻である。
- ・・・写真はどれも顔がむっちり膨れて写っていて、非常に不愉快である。中でも圧巻は、旅館の庭に来た野良ネコを抱き上げている写真であろうか。
- ・・・彼はこの小説を「私の愛児」と呼んでいるが、特に幼いデイヴィドの目を通して描かれた部分は圧巻である。
「圧巻」と「圧倒」の違いは?
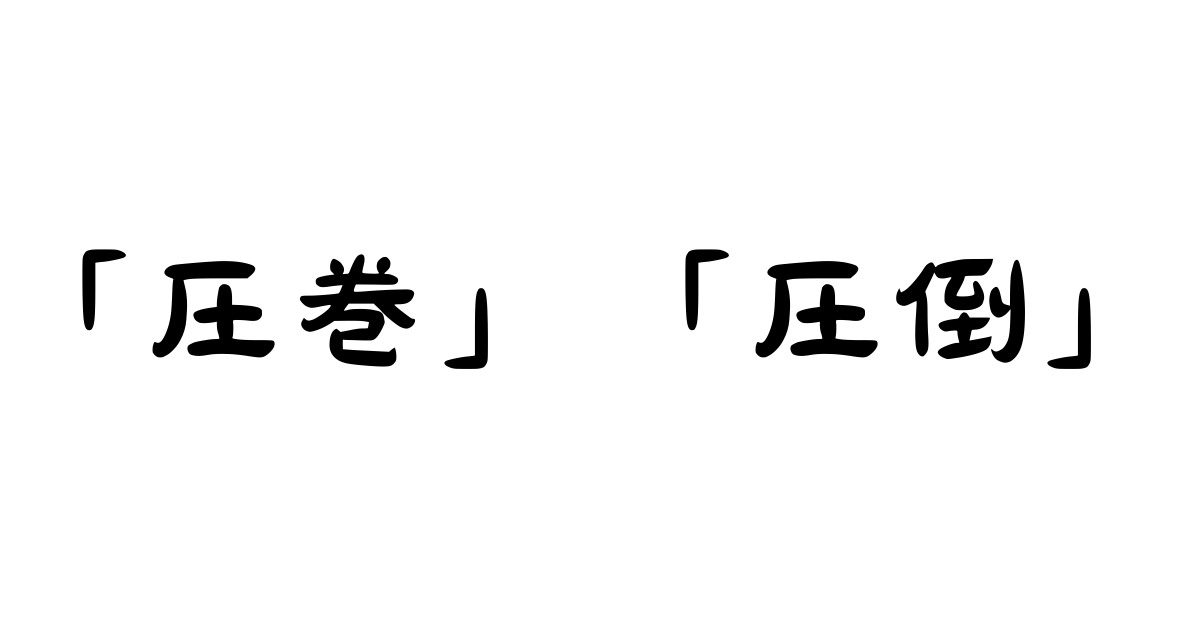
「圧巻」と「圧倒」の違いを見ていきましょう。
「圧巻」は、「全体の中で一番優れた部分」を表す褒め言葉です。身に付けた能力や才能で、どの相手よりも最も優位に立つことを表す言葉です。
「圧倒」は「あっとう」と読み、「他を強い力で押し倒す」という意味が元となり「他とは比べものにならない程の強い力で、相手を打ち負かすこと」の意味があります。ただし、「最も優れる」とか「1番」という意味は入っていません。
「力を使って周囲を押さえつけて、段違いで勝つ」という風な場面で威圧や威嚇のニュアンスを含みながら使われ、あくまで「周りよりも強い」という意味合いの言葉です。
また、「圧倒」は「圧巻」と違い、「圧倒的な弱さ」「圧倒的に負ける」などとマイナスな意味でも使います。
「圧倒」の例
- ・・・米国の政策は、今後ますます否定的で妨害主義的と見做される可能性を強くし、遂には圧倒されてしまうかもしれない。たとえこのような貿易に対する共産中国の能力が弱い
- ・・・、いつもとは違う感じであった。ひたすら懇願するような、祈りにも似たものがみんなを圧倒した。「ああまでいわれるなら…」と、五月三十日に横浜の産貿ホールで公開講座を
- ・・・、脇目もふらずにただひたすらペダルを力強く踏んでいる。その形相の凄まじさと圧倒的なスピードには、首位集団の誰もが息をのまずにいられなかった。 ドイツチームは
「圧巻」「圧倒」の違いまとめ
- 「圧巻」は、「全体の中で一番優れた部分」を表す褒め言葉で、身に付けた能力や才能で、どの相手よりも最も優位に立つことなどを表す。
- 「圧倒」は、「他とは比べものにならない程の強い力で、相手を打ち負かすこと」の意味があるが、「圧巻」のように「最も優れる」という意味は入っていない。またマイナスな意味でも使える。
参考文献
- 編 山田忠雄・柴田武・酒井憲二・倉持保男・上野善道・山田明雄・井島正博・笹原宏之 (2012)『新明解国語辞典』第七版, 三省堂.
- 監 林 四郎 編 篠崎 晃一 ・相澤 正夫・大島 資生(2021)『例解新国語辞典』第十版, 三省堂.
- 編 柴田武・山田進 (2002)『類語大辞典』講談社.
- 編 藤堂明保・松本昭・竹田晃・加納喜光 (2011)『漢字源』改訂第五版, 学研.
- 著 鎌田正・米山寅太郎(2013)『新漢語林』第二版, 大修館.
- 編 松村明・三省堂編修所(2019)『大辞林』第四版.三省堂.
- 公益財団法人日本漢字能力検定協会.「漢字ペディア」.<https://www.kanjipedia.jp/>(参照日2024年10月22日).
- 小学館.「デジタル大辞泉」. <https://dictionary.goo.ne.jp/jn/>(参照日2024年10月22日).