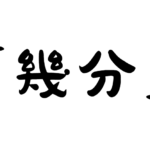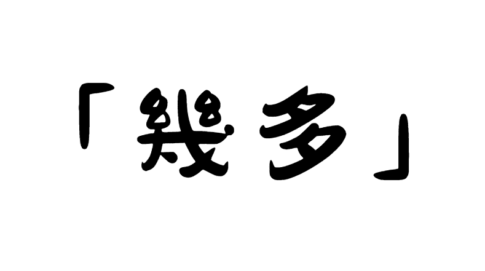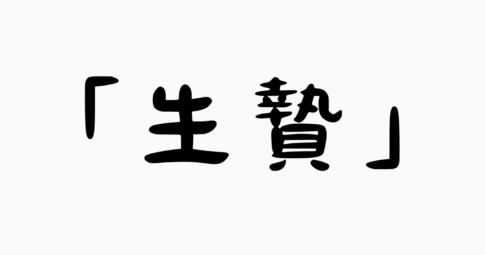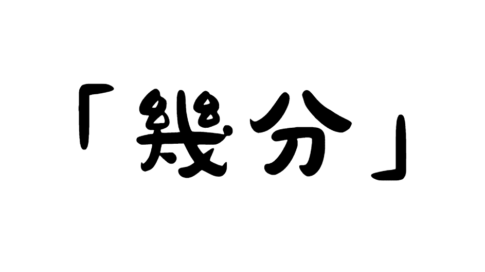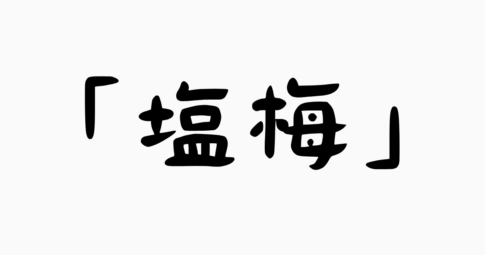「生贄」とは?意味・読み方や類義語は?

「生贄」の意味・読み方!
「生贄」とは、「いけにえ」と読み「人や動物を生きたまま神に供えること。また、その供え物」を意味し、ほかの人やある物事のために生命や名誉・利益を投げ捨てることを言います。
- 豊作を祈願して神に生贄を捧げた。
- この村には若い娘を生贄にする儀式がある。
- 彼は不祥事の責任を取らされ生贄のように処分された。
- 飲み会で上司の生贄になり酔いつぶれた。
などのように使われます。
「生」はセイ、ショウ、「い」きる、「う」まれる、「は」える、「お」う、き、なま、など様々なよみがあり「いきる・いきている間」「うむ・うまれる」「物事が現れる、生ずる」「なま」を意味します。
「贄」はシ、「にえ」とよみ、「手みやげ」を意味します。
「生贄」は「生きている手みやげ」となり「生贄を捧げる」のように使います。
神や精霊に対して、祈願や感謝の意を示すために行うとされるこの行為は、古代から世界各地で行われており、宗教的・儀礼的な意味合いを持っています。
古代社会では、豊作や戦勝、厄除けなどを願って神々に生贄を捧げる風習がありました。例えば、アステカ文明では人身供儀(じんしんくぎ)が盛んに行われ、神への供物として人間が捧げられることもありました。
日本でも古代において「人柱(ひとばしら)」と呼ばれる儀式があり、橋や城の建設時に人を生贄として埋めることで災厄を避けるという信仰がありました。
「生贄」の類義語!
生贄の類義語には「犠牲」「供物」「奉納」などがあります。
犠牲とは「ぎせい」と読み何かのために身を捧げることで、特に命を差し出す場合に使われます。
供物とは「くもつ」と読み神や霊に捧げるもので、動物や人を指すこともあります。
奉納とは「ほうのう」と読み神仏に捧げることで広義では生贄も含むことがあります。
文脈によっては「人柱」「スケープゴート」「殉教」が類似する言葉としてあげられます。
人柱は「ひとばしら」とよみ建築物の安定や神の怒りを鎮めるために人を犠牲にすることを意味し、スケープゴートは他人の罪や責任を負わされる人を指し、比喩的な「生贄」として使われます。
殉教は「じゅんきょう」とよみ宗教のために命を捧げることをいいます。
「生贄」と「殉教」はどちらも命を捧げる行為ですが、意味や目的に違いがあります。
殉教は自らの信仰を貫くために命を捧げることが多く、信仰を貫くための自己犠牲。生贄は神への供物として他者(宗教的権威や集団)によって誰か(またはなにか)が選ばれ、捧げらます。つまり、主体性に大きな違いがあります。
たとえば、キリスト教で迫害された信者が信仰を捨てずに処刑される場合は「殉教」ですが、古代文明で神に捧げられるために捕虜や動物が殺される場合は「生贄」となります。
「生贄」の使い方




「生贄」の例文
- ・・・でしょう。専務は腹の黒い人ですから、それを狙っているのでしょう。わたくしは、その生贄にされたのです。それに…」 友子は必死に訴えつづけた。 「島岡さんは半年ほど前、・・・ 高木 彬光(著)「黒白の囮」
- ・・・、いじめとはまさに生贄そのものだ。クラスなりチームなり、その集団の中で、ひとりを生贄にすることで残りの人間が結束という恩恵を得る。それはむろん恩恵でも何でもないのだ・・・ 大沢 在昌(著)「心では重すぎる」
- ・・・れていた。軍部はなんとかして、国民を鼓舞する必要にかられていた。マタ・ハリはその生贄として利用されたという説もある。 並はずれた美貌に生まれつくというのは、女にとっ・・・ 山崎 洋子(著)「「伝説」になった女たち」
- ・・・代の祭りに淵源があるものと考えられる。当時の祭りは、生産の守護神である御食津神に生贄を捧げたのち、共同体構成員全員で共食するというものであったから、神に捧げる神聖な・・・ 小泉 和子(著)「道具が語る生活史」
「身代わり」「犠牲」の意味・「生贄」との違いは?
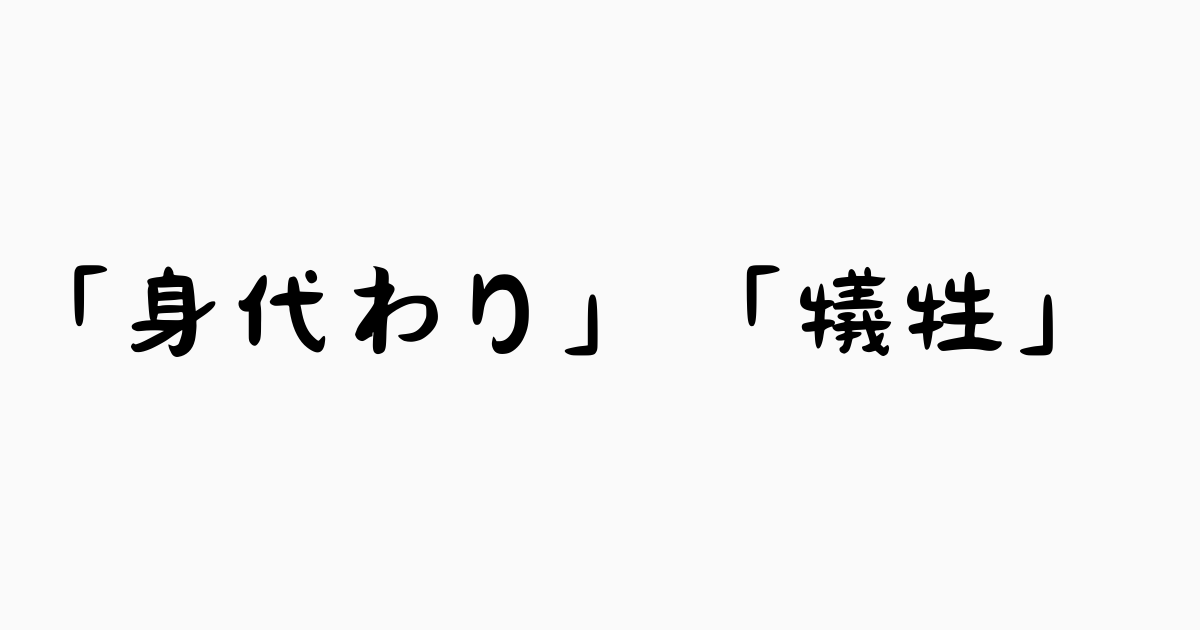
「生贄」「身代わり」「犠牲」は似た意味を持ちますが、ニュアンスや使われ方が異なります。
生贄は神や霊に供えるために人や動物を捧げることをいいます。
身代わりは「本人の代わりに、本人に見せかけて用いるにせもの」を意味し、その本人の代わりになんらかの不利益を被るという意味が込められています。「誰かの身代わりになる」「身代わり人形」のように使われます。
犠牲はある目的のために損失となることをいとわず、大切なものを捧げることのほか、「災難などで死んだり負傷したりすること」の意味も持ちます。宗教・戦争・事故などで「犠牲をはらう」「戦争の犠牲者」のように使われます。
生贄は神や霊への供物という宗教的な意味が強く、身代わりは他者の代わりに何かを引き受ける点が特徴となります。犠牲はより広い意味で使われ、目的のために命や何かを失うことを指します。
参考文献
- 編 松村明・三省堂編修所(2019)『大辞林』第四版.三省堂.
- 編著 北原保雄 (2010)『明鏡国語辞典』第二版, 大修館書店.
- 小学館.「デジタル大辞泉」. <https://dictionary.goo.ne.jp/jn/>(参照日2025年2月14日).
- 公益財団法人日本漢字能力検定協会.「漢字ペディア」.<https://www.kanjipedia.jp/>(参照日2025年2月14日)
- 倉持保男・上野善道・山田明雄・井島正博・笹原宏之 (2011)『新明解国語辞典』第七版, 編 山田忠雄・三省堂.