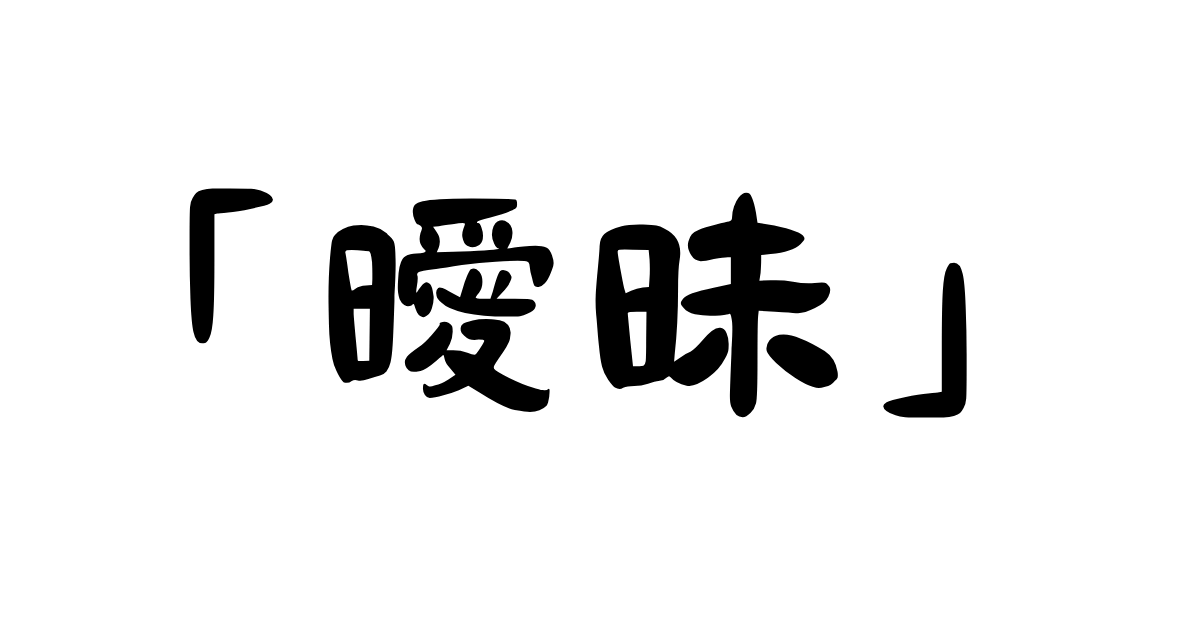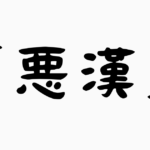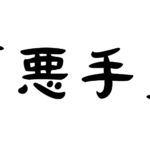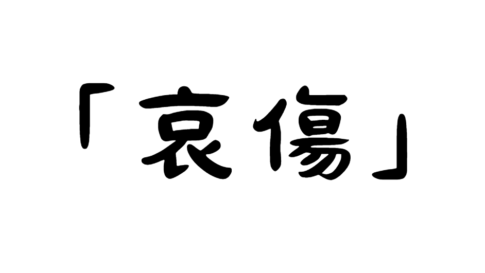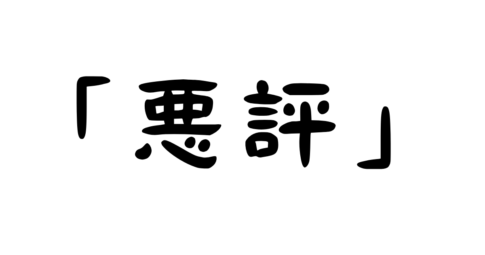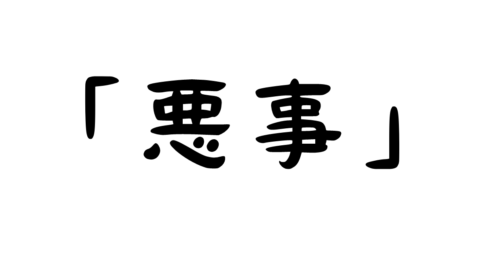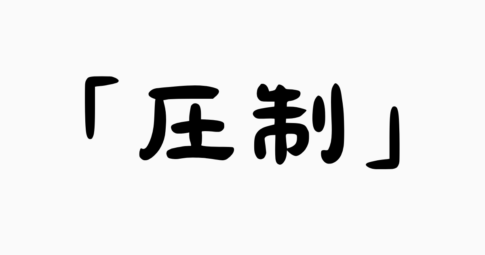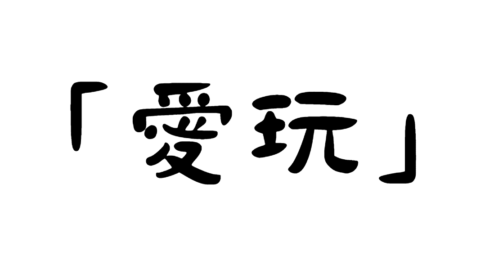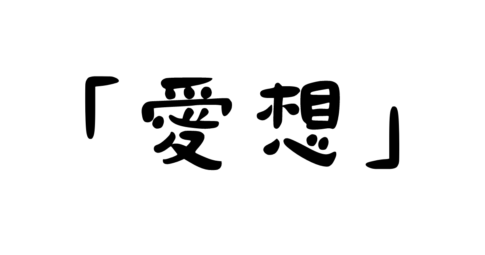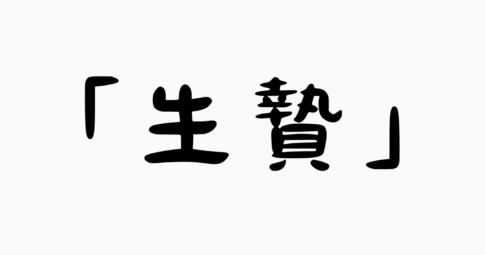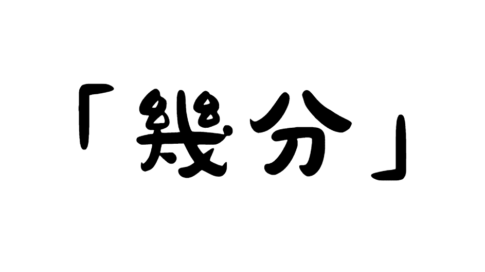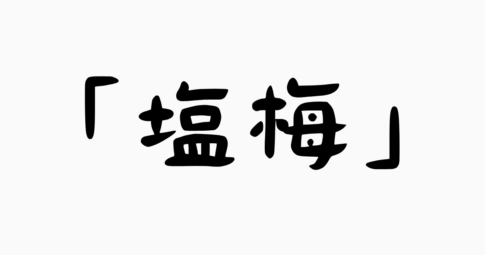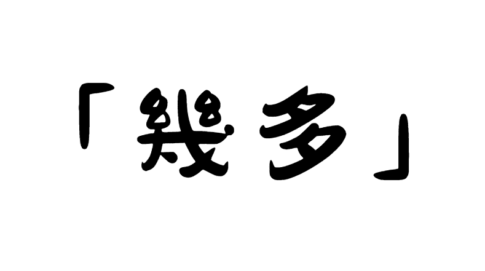「曖昧」とは?意味・読み方や類義語・対義語は?
「曖昧(あいまい)」は、「言葉や態度がはっきりせず、意味がとりにくい様子。疑わしいさま」を指します。
一般的にはっきりしない状況を「曖昧な」と表現しますが、わざと分かりにくくしたり、あえて明確にしないなど、故意に「曖昧」にしておくこともあります。
- うちの上司はいつも曖昧な指示しか出さないので困る。
- 私は考えていることをそのまま口にせず、曖昧な言い方をすることにした。
- その証人たちすべての答えは曖昧で、視線は宙を泳いでいた。
- 英語は苦手で特に文法は曖昧な知識しか私にはなかった。
などのように使われます。
「曖昧」の「曖」は「薄暗い、ぼんやりしている」という意味、「昧」は「暗い、道理に暗い」などの意味を含みます。
これらを合わせた「曖昧」は、「物事が明確でない」「知識や理解がはっきりしない」という状態を表す言葉です。
例えば、イエスかノーかはっきりしない返事のことを「曖昧な返事」、どっちつかずではっきりしない態度のことを「曖昧な態度」、正確性に欠ける説明のことを「曖昧な説明」などといいます。
場合によっては仕事や人間関係に悪影響にもなる「曖昧」ですが、これは、本人がわざとそうしている場合と、そうでない場合があります。
例えば、本人が意図せず態度が曖昧になってしまう場合もあれば、断りにくくわざと曖昧な返事をする場合もあります。
また、知識不足や、経験が浅いために説明が曖昧になってしまう場合と、わざと情報を絞るなどして説明を曖昧にする場合もあります。
これは、立場や状況によって、敢えて曖昧にしておくことが好都合なこともあるからです。
ただし、相手に対して「曖昧」であることを指摘する際は、非難する意味合いを含む言葉になるので、使い方には注意が必要です。
例えば、「いい感じの説明資料作っておいて」と指示された際、「そんな曖昧な指示ではわかりません。」と返すよりも、「少々要領を得ないので、もう少し詳しい指示をお願いします。」や「おぼろげなイメージしか浮かばないので、もう少し詳しい指示をお願いします。」の方がいいかもしれません。
「曖昧」の類義語には、「模糊(もこ)」「どっちつかず」「うやむや」などがあります。
「曖昧模糊(あいまいもこ)」は、「曖昧」も「模糊」もはっきりと分からない状態を意味するので、二重になり意味を強調しています
「曖昧」の対義語には、「明確」「はっきり」「明白」などがあります。
「曖昧」の使い方




「曖昧」の例文
- ・・・手段となる道具さえ欠いているのです。 また、伝統とか現代化とか発展といった術語は曖昧さに満ちた言葉であって、こうした術語をどのように定義するかといった合意は、いまの・・・モハンマド・ハタミ(著)/ 平野 次郎(訳)「文明の対話」
- ・・・な眼差しで「結婚」という言葉を口にした。あのとき、戸惑い、稲葉から目をそらした。曖昧な返事をした。後悔だけが残る。後悔だけが、遺された空間に、静かに旋回する。 稲葉・・・北林 優(著)「ミッドナイトブルー 警視庁鑑識課」
- ・・・てくる。 「シンシアといいます。日本から観光旅行ですか?」 「まあね」 高見沢は曖昧に答える。 「わたし、国立モザンビア大学でアフリカ考古学を勉強してるの。休暇を取・・・大藪 春彦(著)「凶獣の罠」
- ・・・ゃぁ外人部隊だったって噂まで出ているが、それは本当なのか。その辺のこたぁみんな、曖昧模糊とした闇の中ってぇ奴のままだ」 それに、肝心の志波銀次はどうなったのかってこ・・・西村 健(著)「脱出」
「曖昧」「あやふや」「うやむや」の違いは?
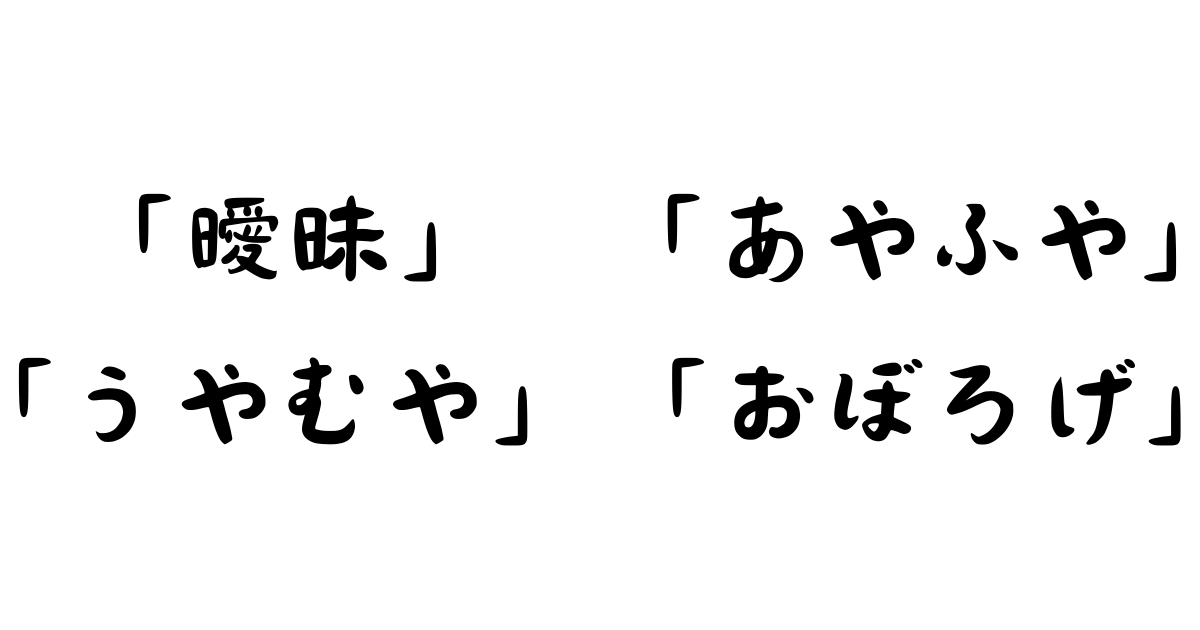
「曖昧」「あやふや」「うやむや」「おぼろげ」のそれぞれの違いを見ていきましょう。
「曖昧」は、「物事が明確でない」「知識や理解がはっきりしない」という状態を表す言葉です。
そして、この「曖昧」な状態には、本人がわざとそうしている場合と、そうでない場合があります。
「あやふや」は、「不審し(あやし)」の語根を取った、「あやふし(危)」が語源、「啊呀乎呀」の漢字、など考えられる語源がいくつかあります。
いずれにしても、「あやふや」は「はっきりとせず不確かな様子」を表現する言葉です。
「曖昧」と「あやふや」はほぼ同じ意味を持つ類義語ですが、「曖昧」は「あやふや」よりもかしこまった言い方になります。
ですから、友人には「その説明はあやふやだね…」で済ませても、学術論文の指摘など、かしこまった時に使うには「研究目的の定義が曖昧である。」とした方がよいですし、場面での使い分けが求められます。
また、「曖昧」はわざと「曖昧」にする、ことがありますが、「あやふや」は「になる」と使用されることが多くあります。
例えば、「昨日のことが、なんだか急にあやふやになる。」「事実さえあやふやになっている。」などと使い、「あやふや」は、わざとではなく本当に、本人でさえも気持ちや考えがぼんやりしていることや信頼性が低い状態を指しています。
このように、「あやふや」は、確かな根拠が不足している場合や根本的な部分がはっきりと定まっていない場合に使います。
「あやふや」の例
- ・・・登場するが、その一例として、「バンド」をとりあげてみよう。とはいえ、ここは小生の あやふやな説明ではなく、平凡社世界大百科事典からの以下の抜粋を一読していただくのが賢明と・・・栗山 洋児(著)「カスター将軍最期の日」
- ・・・はすでに述べたとほりだが、法律の文章となればなほさらだらう。法律がどうとも取れるあやふやな口のきき方をしたのでは、あぶなつかしくて仕方がないのだ。そしてその曖昧なものの・・・丸谷 才一(著)「文章読本」
- ・・・とんどが外注。管理者であるホームセンターの目が現場に行き届かず、施工管理の責任があやふや になる可能性も否めません。何かトラブルが起きたとき、こういう状態は非常に困った問・・・阿部 邑紀(著)「値段の秘密 『ウラ』から見る経済・法律・流通のしくみ」
「うやむや」は、「物事がはっきりしない様子、いい加減な様子」を意味し「有耶無耶」と書く四字熟語です。
もともと、「うやむや」は、仏教用語で僧侶の問答の「有耶?無耶?(うや?むや?)」(あるのか?ないのか?)から来ています。
ただ、あるのか?ないのか?のように、白黒はっきりさせるための質問であった「有耶無耶(うやむや)」ですが、 答えが曖昧なものばかりで、 結局その答えに対して「うやむや」という言葉が使われるようになってしまったといわれています。
「うやむや」の例
- ・・・とは何か。それだけを考えていた。会社はどのみち倒産する。そのどさくさにまぎれて、うやむやにしようと考えていた五十億である。そうした金のために家族を犠牲にはできなかった。・・・梁 石日(著)「裏と表」
- ・・・で、この上は自然の成行きに任せるよりほかはないと組頭も決心したらしく、詮議は結局うやむやに終った。 組頭が立去ったあとで、三上は福井に言った。 「組頭の前でそんなに強情・・・岡本 綺堂(著)「白髪鬼」
- ・・・なの意見の代弁者として、目上に対しても議論をふっかけることも多いでしょう。物事をうやむやにするのが嫌いで、白黒つけたくなるのもこの時期の特徴です。まるで正義の味方のごと・・・松村 潔(著)「未来事典 3年後の私がわかるサビアン占星術」
「おぼろげ」は、「朧げ」と書き「記憶などが不確かである状況」を表す言葉です。
主に視覚的な曖昧さや記憶が曖昧でよく覚えていない、肝心なところを忘れているといった意味で使います。
また「朧げ」は、月が雲や霞にさえぎられて、ぼんやりとしているさまを指し、自然界の曖昧な美しさを象徴する言葉としても使われています。
このような背景があるため、「おぼろげ」は、不確かさや「曖昧」さを表すのと同時に、断定や黒白つけずに伝える日本的な表現と言えるかもしれません。
- 「おぼろげ」の例
- ・・・たしたちは東の通廊をとおって、そこにいった。 西の通廊は、ふりしきる雪のむこうにおぼろげに影が見えただけだったが、館全体が左右対称形なのは、なんとなく想像がついた。 北・・・津原 泰水(著)「ようこそ雪の館へ ルピナス探偵団」
- ・・・るも任意である。 チェックポイントという言葉で、「ゲーム」なるもののイメージが、おぼろげに浮かんできた。たぶん、ラリーの要領で定められたチェックポイントを通過して、最終・・・貴志 祐介(著)「クリムゾンの迷宮」
- ・・・ていって、やがては最終的な平衡状態に達するだろう。 他の科学者たちは、この考えをおぼろげな遠い過去にまでさかのぼって適用した場合、その帰結がどうなるかを検討しはじめた。・・・ジョン・バロウ(著)/ 松田 卓也(訳)「宇宙が始まるとき」
「曖昧」「あやふや」「うやむや」「おぼろげ」の違いまとめ
- 「曖昧」は、「物事がはっきりしない状態」や「わざとはっきりさせない」ときに使い、ビジネスや文書などかしこまった場面でも多用されます。
- 「あやふや」は「曖昧」と同じ「はっきりとせず不確かな様子」を指しますが、「曖昧」よりも俗語的です。そして、信頼性が低いときや確かな根拠が不足している場合に使います。
- 「うやむや」は、意図的な「曖昧」さを強く表す言葉で、問題を避けるためあえてなにかをごまかしたい時に使います。
- 「おぼろげ」は、「曖昧」と同様に「ぼんやり、物事がはっきりしないさま」という意味合いですが、特に漠然とした記憶や不鮮明な視覚に対して使います。
参考文献
- 編 山田忠雄・柴田武・酒井憲二・倉持保男・上野善道・山田明雄・井島正博・笹原宏之 (2012)『新明解国語辞典』第七版, 三省堂.
- 監 林 四郎 編 篠崎 晃一 ・相澤 正夫・大島 資生(2021)『例解新国語辞典』第十版, 三省堂.
- 編 柴田武・山田進 (2002)『類語大辞典』講談社.
- 編 藤堂明保・松本昭・竹田晃・加納喜光 (2011)『漢字源』改訂第五版, 学研.
- 著 鎌田正・米山寅太郎(2013)『新漢語林』第二版, 大修館.
- 編 松村明・三省堂編修所(2019)『大辞林』第四版.三省堂.
- 公益財団法人日本漢字能力検定協会.「漢字ペディア」.<https://www.kanjipedia.jp/>(参照日2024年11月14日).
- 小学館.「デジタル大辞泉」. <https://dictionary.goo.ne.jp/jn/>(参照日2024年11月14日).