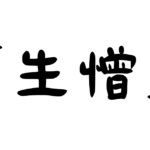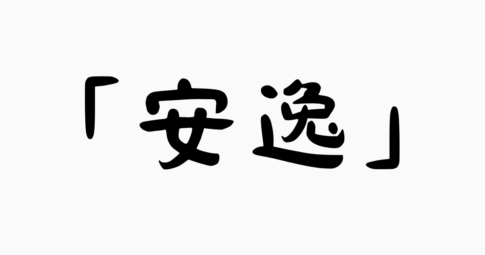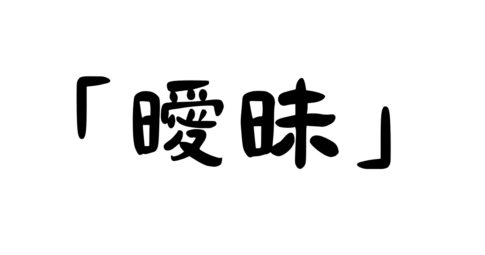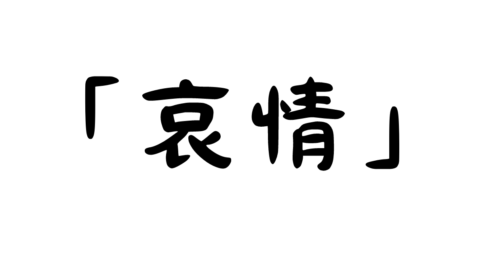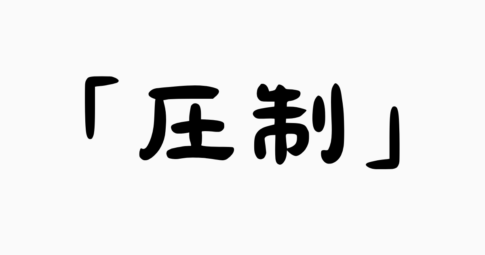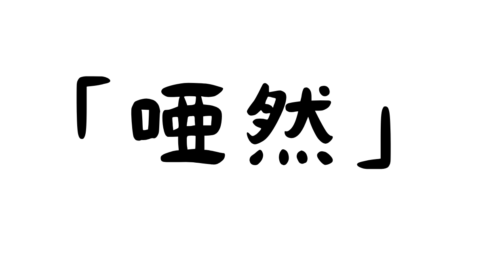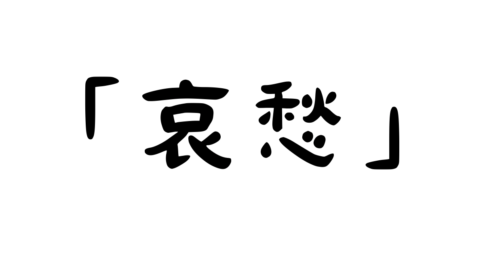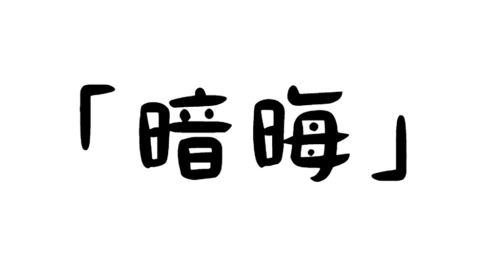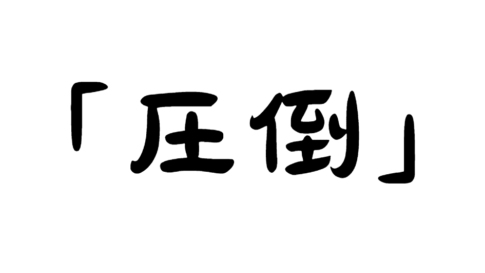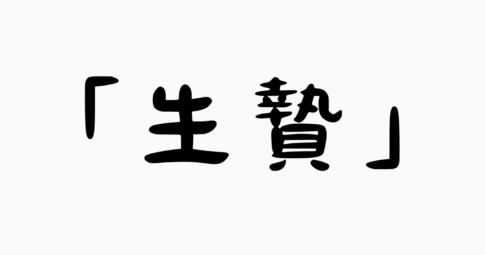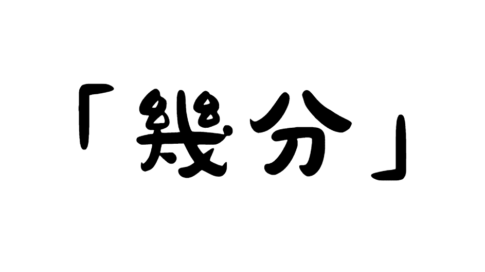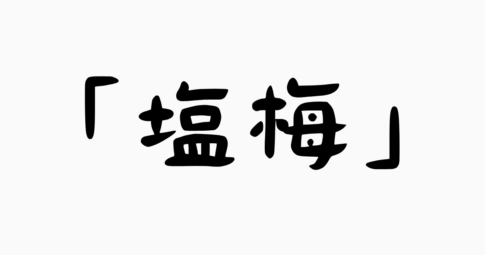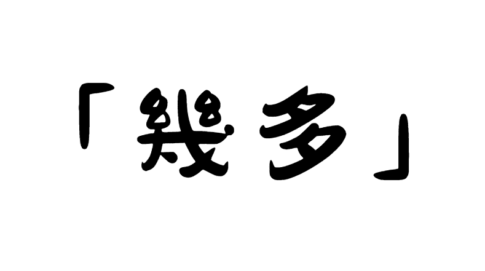「阿漕」とは
「阿漕」とは、「欲深く、ずるいこと」を意味する言葉です。
特に、他人に迷惑をかけたり、道徳に反した行為をする様子を表現する際に使われます。
また「阿漕」には「しつこい」という意味もあります。
- 阿漕な商売をしている
- 阿漕な手段を選ぶ
- 阿漕な計画
- 阿漕な行動をする
などのように使われます。
「阿漕」は、三重県津市の阿漕ヶ浦(あこぎがうら)で伝わる「阿漕平治の伝説」が由来とされています。「阿漕」という言葉は卑怯な印象があり、阿漕ヶ浦で密漁が見つかり、海に沈められたという男の話なので、卑怯というのは間違いないかもしれません。
ただ、三重県の阿漕ヶ浦では、この男は親孝行のために密漁をしたともいわれており、親孝行な子どもの悲しい話として伝えられています。
「阿漕」の類義語として「狡猾」「卑怯」「不正」「詐欺」「姑息」などがあります。
「阿漕」の対義語として「正直」「誠実」「公正」「真摯」「清廉」などがあります。
「阿漕」の使い方

ぼくお店を開くことにしたんだ!

阿漕な商売をしているって本当?

まさか!誠実な心で働いているよ!

なんだ〜よかった!お仕事頑張ってね!
「阿漕」の例文
- ・・・極楽へ送ったと告げ、法華経の利益を賛える。ほかに野守・皇帝・鍾馗など。三、幽霊(阿漕・求塚など)善知鳥(前シテ老人。ツレ猟師の妻。子方稚児。ワキ僧) 立山禅定の僧、・・・中森 晶三(著)『「能」が今、教えてくれること』
- ・・・、さらに平舞台へも客をあげたので、大道具の置き場もないほどになった。 「中村座も阿漕なことをする」「こんなに押し込んでどうするんだ。おちおち芝居を見ることもできな・・・ 皆川 博子(著)「花櫓」
- ・・・た名殘と言へよう。「羽束師の森」「來背の森」「糺の森」「轉寢の森」「木枯の森」「阿漕が浦」「風莫の浦」「松帆の浦」「手結の浦」、名に從つて自然が創られ、その自然が物・・・塚本 邦雄(著)「国語精粋記」
「阿漕な商売」とは
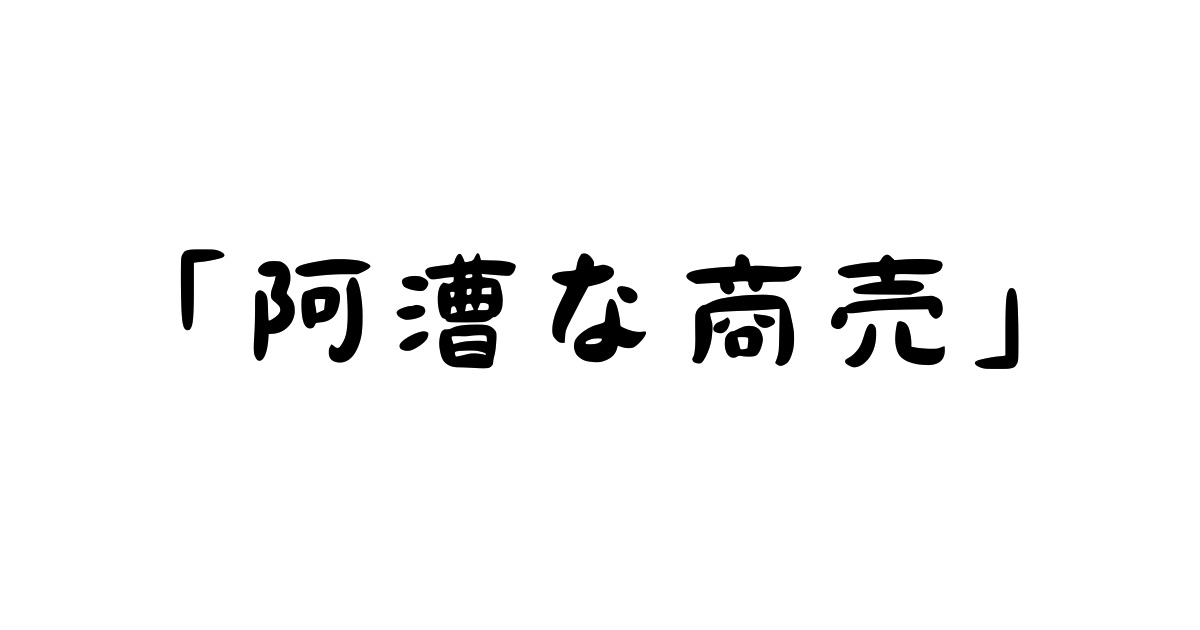
「阿漕な商売」とは、道徳的に問題のある、不正直または不正な手段を用いた商売を表します。
例えば、消費者や取引先を欺くために虚偽の情報を提供したり、品質や条件について嘘をついたりすること。市場価格よりも不当に高い価格で商品やサービスを販売すること。法律や倫理に反する方法で利益を追求することなどがあります。
上述のように、元々は、三重県津市の「阿漕ヶ浦」という場所に由来し、そこで繰り返し禁漁を行ったことから「阿漕=ずるい、しつこい」という意味が生まれました。
現代では、主に道理に反した行動や、強欲な行為などに対して使われています。
参考文献
- 編 松村明・三省堂編修所(2019)『大辞林』第四版.三省堂.
- 編 山田忠雄・柴田武・酒井憲二・倉持保男・上野善道・山田明雄・井島正博・笹原宏之 (2011)『新明解国語辞典』第七版, 三省堂.
- 公益財団法人日本漢字能力検定協会.「漢字ペディア」.<https://www.kanjipedia.jp/>(参照日2024年9月12日).
- 小学館.「デジタル大辞泉」. <https://dictionary.goo.ne.jp/jn/>(参照日2024年9月12日).

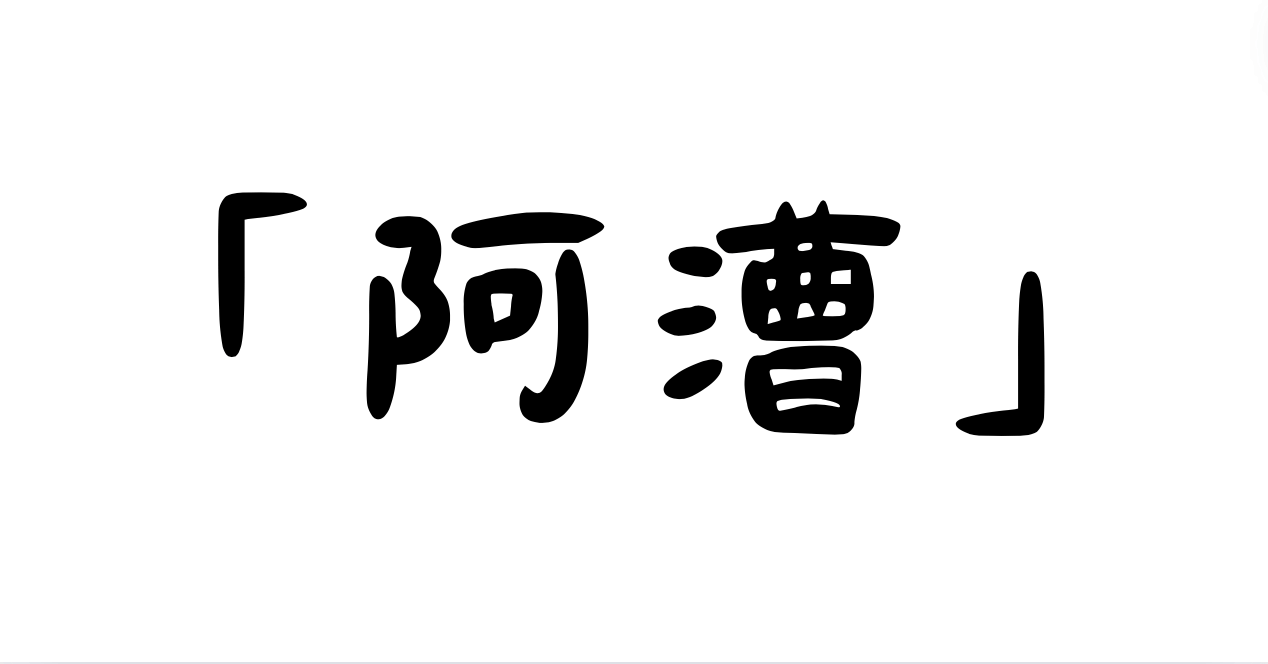
-150x150.png)