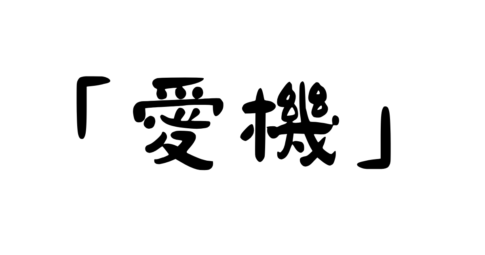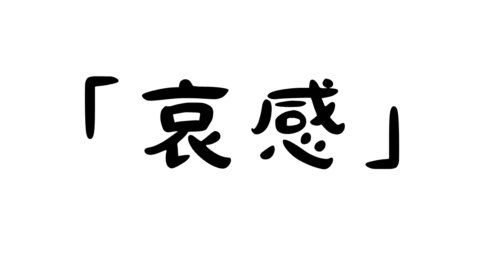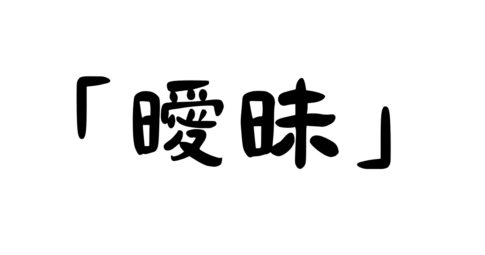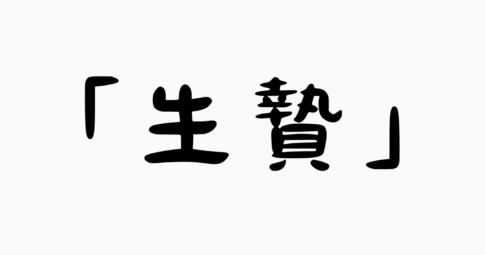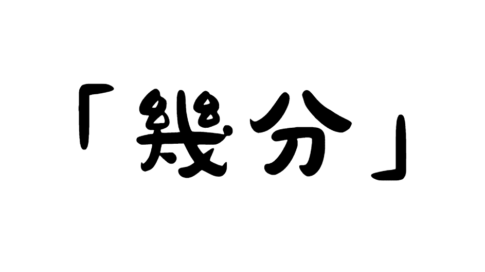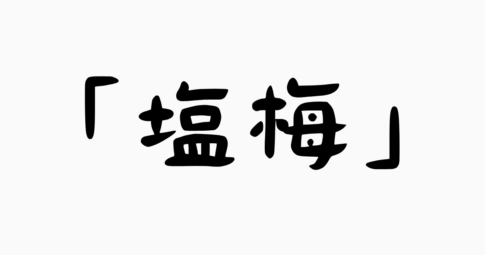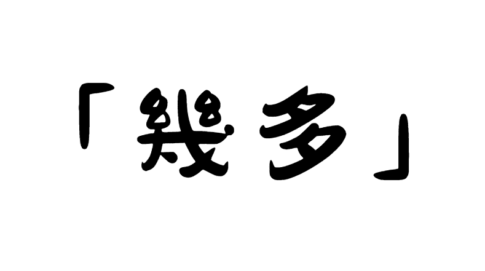「悪評」とは
「悪評(あくひょう)」は、「特定の人や物事に対するよくない評価やうわさ。悪い批評」を指します。
その人や物事に対する否定的な感情や意見で悪評があると、そのものの信頼性や評価が低いと認知されやすいです。
- あの化粧品はSNSの口コミから悪評が広まってしまい、売り上げが落ちている。
- その映画は批評家からの悪評が多かったため、入場者数が少ないらしい。
- 近所でも学校内でも彼の悪評を耳にしたことはない。
- ボクの発言が差別的だと捉えられ、悪評を買ってしまった。
などのように使われます。
「悪評」の「悪」は、「好ましくない、よくない」といった意味で、「評」は「物のよしあしをはかる。しなさだめする」ことです。
ですから「悪評」は、「よくない評価」「悪い批評」を指し、その人や物事に対する否定的な感情を表す言葉です。
例えば、通販サイトのカスタマーレビューで、「この布団ではぐっすり眠れない★☆☆☆☆1」「配達の時間指定をしたのに届かなかった★☆☆☆☆1」「この毛布を使った翌朝、ダニに刺されていた★☆☆☆☆1」などと書かれていたとしたら、購入者の不満を表す「悪評」といえます。
ただ、それはあくまで、その商品に対する「個人的な感想や意見」です。
「眠れなかったり」や「ダニに刺されたり」した原因が寝具にあるという事実は証明されていないし、「配送」に関しては寝具自体の評価とは関係ないと言えます。
しかし、寝具の購入を迷っている人がその「悪評」を読んだたときに、購入を控える可能性がありそうです。
つまり「悪評」は評価する側の個人的な見解であり、当事者の本質や事実とは必ずしも一致しないのですが、「悪評」があること自体が、当事者の信頼性は低く、価値がないと印象づける可能性があります。
「悪評」の類義語には、「悪名」「汚名」「酷評」などがあります
「悪評」の対義語には、「好評」「高評価」「名声」などがあります。
ところで、「悪名は無名に勝る」という言葉があります。
世に知られるきっかけが悪評であったとしても、まるで世の中に知られていない状態よりはずっとよい、といった意味合いで用いられる言葉です。
良い評判で有名になるのが一番いいが、ビジネスや芸能ではなかなか難しい、ならば悪い評判でも有名になりたいと考えてしまうということです。
ただし、いくら注目を浴びても悪評が立つと、様々な問題視される点が出てくる可能性もあるでしょう。
「悪評」の使い方




「悪評」の例文
- ・・・堂は年来の友たる中村彌六を失って痛かろう。中村彌六もこのままでは政界から葬られ、悪評は死ぬまでつきまとう。一人の男を生ける屍にしてどんな利益があるというのか。こんな
- ・・・した。 同じジャーナリストのご好意を、身にしみてありがたいと感じるこの頃です。悪評も、もちろん多くあり、その中には、事実無根や誤解も当然ありますが、的確なご指摘も
- ・・・した胎盤を原料にしているとマスメディアに喧伝されれば、化粧品会社との提携以上に、悪評をたてられる。しかも、その胎盤の所有権がいったい病院にあるのかという法的問題まで・・・帚木 蓬生(著)「エンブリオ」
- ・・・さそうことにしていた。 「嘉兵衛」という名は、そういう場合にきくのである。すべて悪評で、その若者をほめる言葉を一度もきいたことがない。 その理由の大部分は、嘉兵衛が・・・司馬 遼太郎(著)「菜の花の沖」
「悪評が立つ」とは?
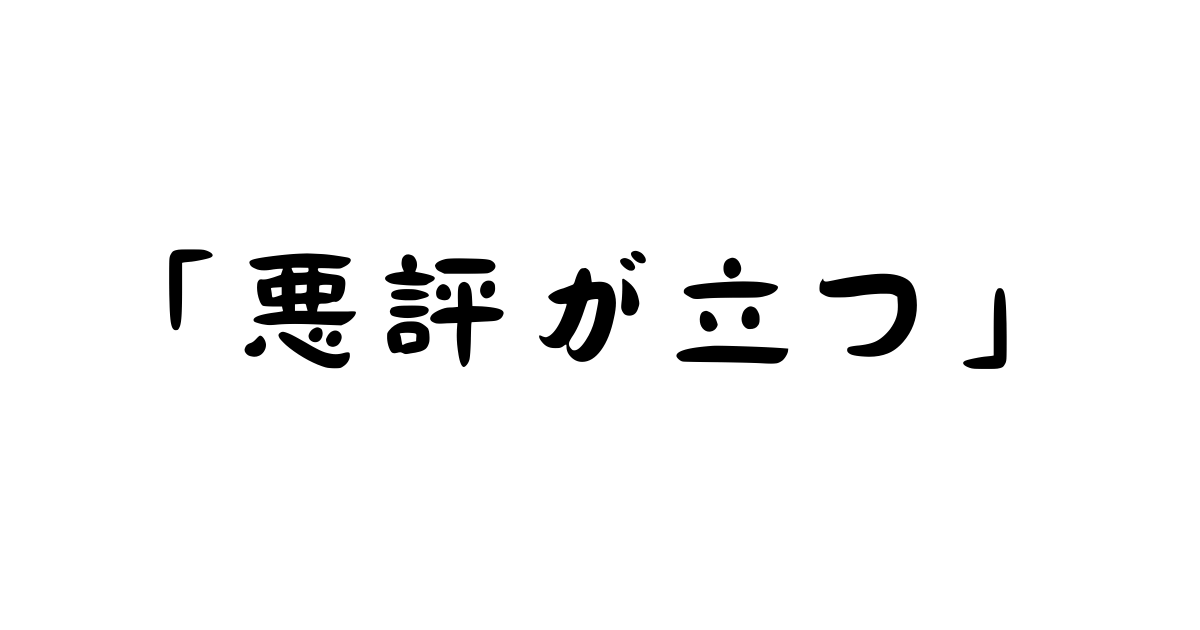
「悪評」は「悪いうわさや評判」という意味、「立つ」は「世に知れ渡る」という意味ですから、「悪評が立つ」は、「悪いうわさや批評が人に知れわたる。世間に広まること」ことを指します。
個人や商品、サービスなどについて、悪い評価が広まる時に使われます。
例えば、現代はネット社会のため、購入後のレビューに商品への不満や店員へのイラ立ちを投稿して、それが関係のない一般の人に段々と広まってしまうことが多くあります。
また、場合によっては妬みややっかみと言った感情があるだけで問題が何も無いところから急に悪い評判が広まって「悪評が立つ」こともあります。
もちろん「悪評」が悪いものとばかりは言えず、商品やサービスに対する正当な評価として、改善するための視点になったり、購入したい人の情報源として活用できる側面もあります。
ただし、「悪評」は、それ自体がその人や商品等の印象を悪くさせるような内容ですから、それが事実かどうかは別として一度でも「悪評が立つ」と、それを鵜呑みにしてしまう人もいるのです。
そして、「悪評」が立ってしまったら、終息するのは難しく、消えるまでにはある程度の時間がかかります。
参考文献
- 編 山田忠雄・柴田武・酒井憲二・倉持保男・上野善道・山田明雄・井島正博・笹原宏之 (2012)『新明解国語辞典』第七版, 三省堂.
- 監 林 四郎 編 篠崎 晃一 ・相澤 正夫・大島 資生(2021)『例解新国語辞典』第十版, 三省堂.
- 編 柴田武・山田進 (2002)『類語大辞典』講談社.
- 編 藤堂明保・松本昭・竹田晃・加納喜光 (2011)『漢字源』改訂第五版, 学研.
- 著 鎌田正・米山寅太郎(2013)『新漢語林』第二版, 大修館.
- 編 松村明・三省堂編修所(2019)『大辞林』第四版.三省堂.
- 公益財団法人日本漢字能力検定協会.「漢字ペディア」.<https://www.kanjipedia.jp/>(参照日2024年11月15日).
- 小学館.「デジタル大辞泉」. <https://dictionary.goo.ne.jp/jn/>(参照日2024年11月15日).

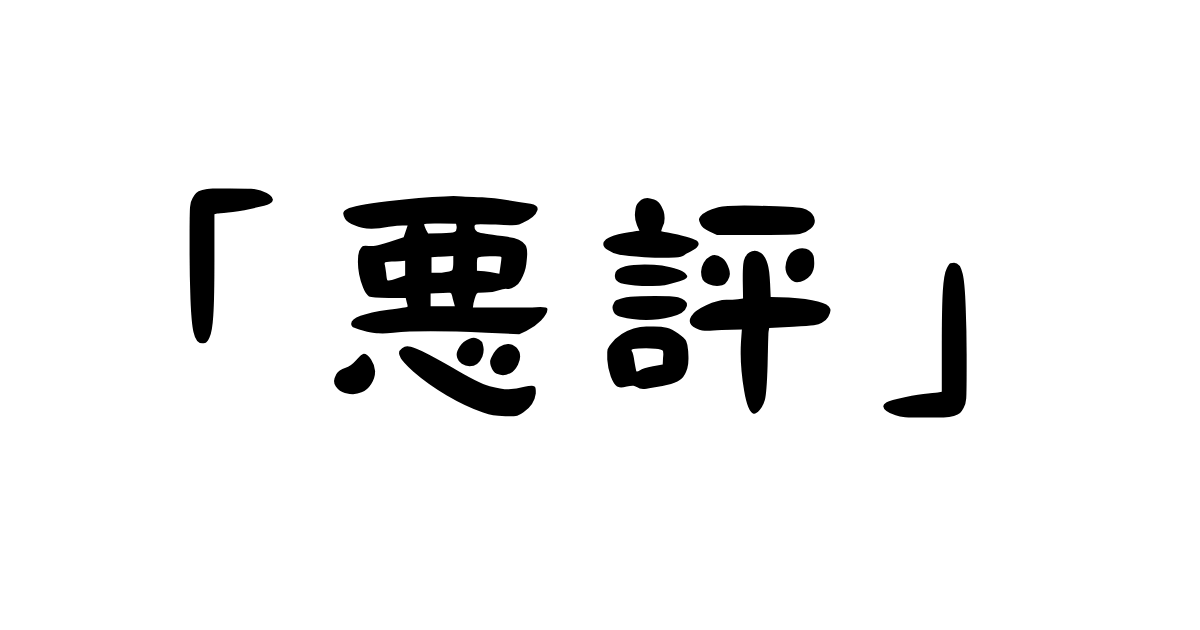
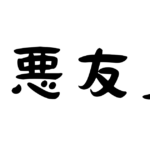
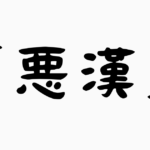

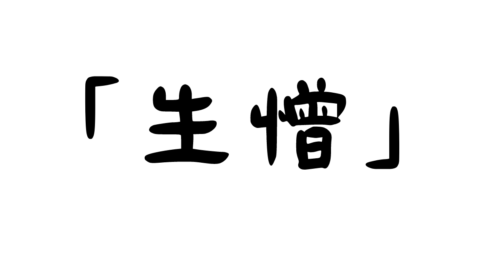
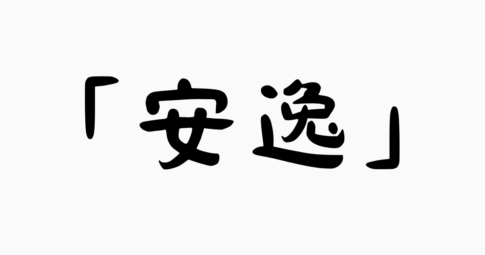

-485x255.png)