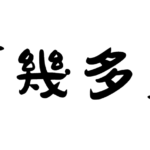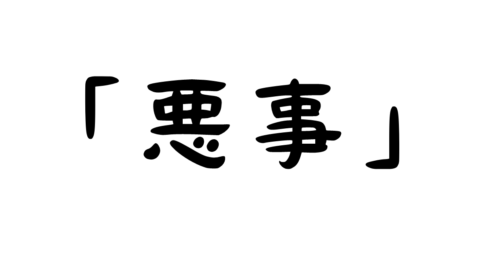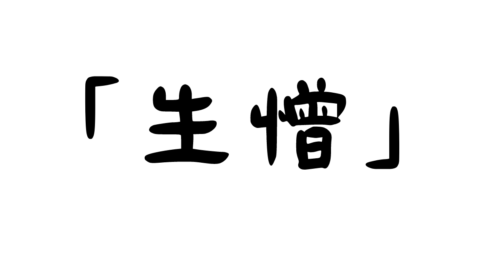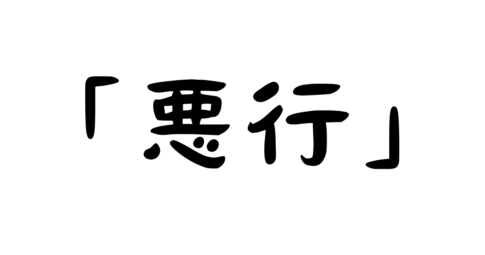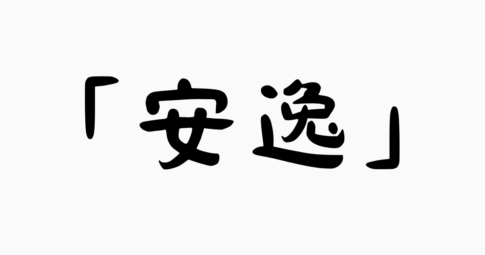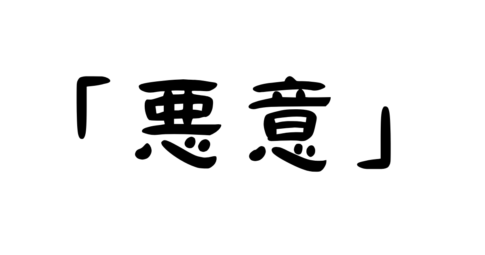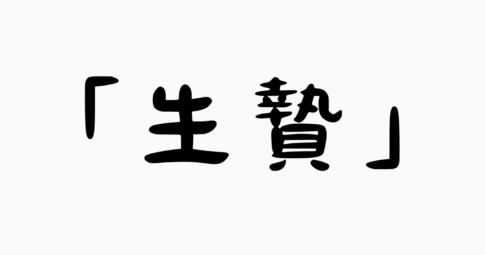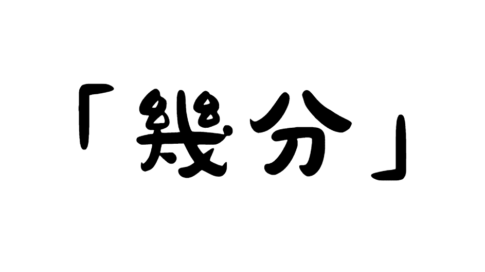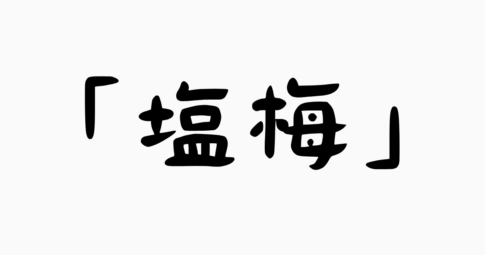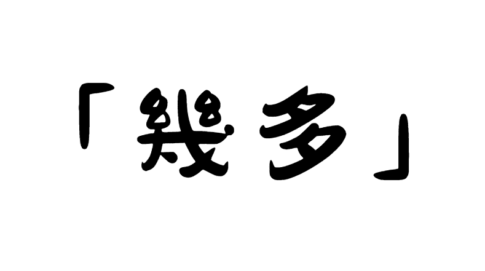「塩梅」とは?意味・読み方や語源由来・類義語は?
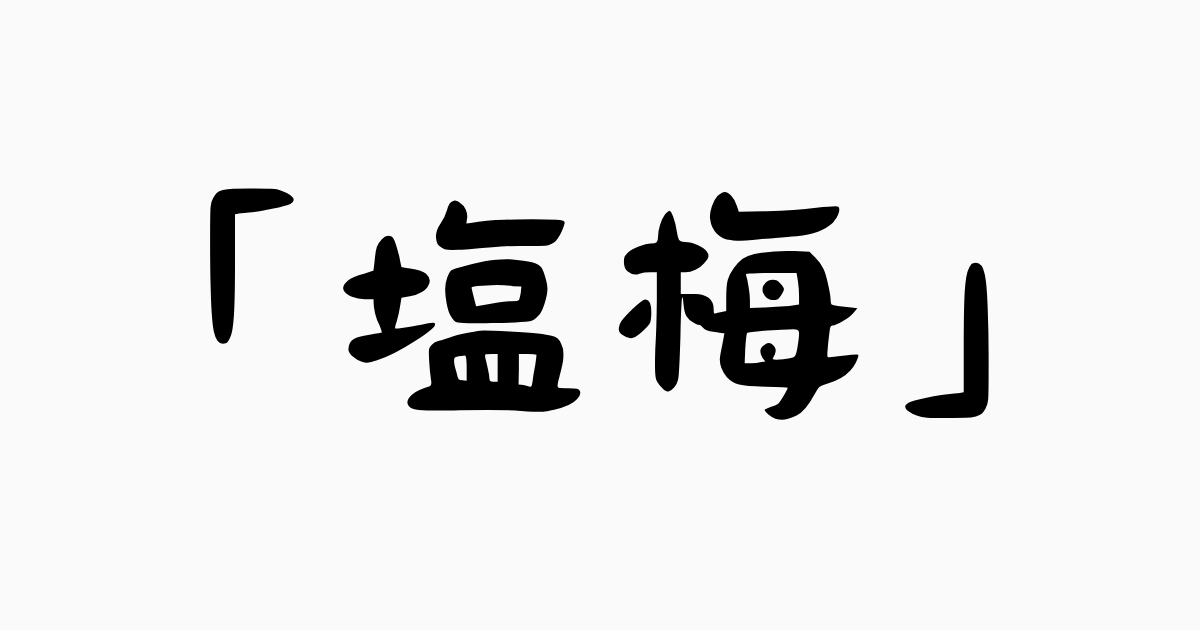
「塩梅」の意味・読み方!
「塩梅」とは、「あんばい」と読み「料理の味加減」「物事の具合、調子、加減」「からだの具合」を意味する言葉です。
味の基本である塩と梅(えんばい)と、物を具合よく並べる意味の「按排・按配(あんばい)」とが混合した語で、料理の味加減以外の意味では「案配」とも書きます。
- 最近は寒い日が続き体の塩梅がよくない。
- この煮つけはいい塩梅に出来ているね。
- プロジェクトがいい塩梅で進んでいる。
- 塩梅をみてスケジュールを組もう。
などのように使われます。
「塩梅」の語源由来と類義語!
「塩梅」とは、元は料理における味の調整のことを指しており、まだ食酢がなかった時代は塩と梅酢を使って料理の味付けをしていました。
そして「味をちょうどいい加減にする」という意味合いが「塩梅」の語源であり、そこから転じて広く「物事のバランスや調整」を意味するようになりました。
「塩梅」の類義語には、「加減」「調子」「具合」などがあります。
「加減」「調子」「具合」は、状況や状態、程度を表す言葉で使われ、物事の状態やバランス、適切さを表す意味になります。
それぞれの特徴として「加減」は物事の程度や調整を指す実用的な表現であり「いい加減」や「無理加減」のように良くない意味でも使われます。
「調子」は状態の動きの良し悪し、リズム感を表し身体的・精神的な状態、機械の動作にも使います。「調子に乗る」のように比喩表現でも使われます。
「具合」は物事の具体的なありさま、状態を指し状況や事柄の適合性、健康状態にも使います。
「塩梅」の使い方




「塩梅」の例文
- ・・・ますよ。なんというか、自分に浴びせられた悪態が、ぐるぐると頭の中を駆け巡るような塩梅でして、もう腹が立って、腹が立って、まだまだ顔もみたくないと、そんな感じに違いあ・・・ 佐藤 賢一(著)「二人のガスコン」
- ・・・がして、狭い家の中を掃くのさえ、中腰になって、せいせいといい、よほど苦しいような塩梅である。私は、どうも、これはいけないと思い、何んとかせんければと心を痛めました。・・・ 高村 光雲(著)「幕末維新懐古談」
- ・・・里の道を歩かにゃならん。それが姉さんには何もないのに魔法のやうに出て来る。こげな塩梅の上等な物は東京にもありゃせんぞ。欲を云へば、焼酎でもあれば、これより御馳走はな・・・ 三角 寛(著)「つけもの大学」
- ・・・世界の住人たる「学者」や「評論家」を呼んできて一席ぶたせて、能事終れり、といった塩梅なのである。しかも、そんな儀式に呼んだほうも呼ばれたほうも結構満足して、「民主的・・・ 津田 道夫(著)「インクルージョンへの道」
「ちょうどいい塩梅」の意味とは?
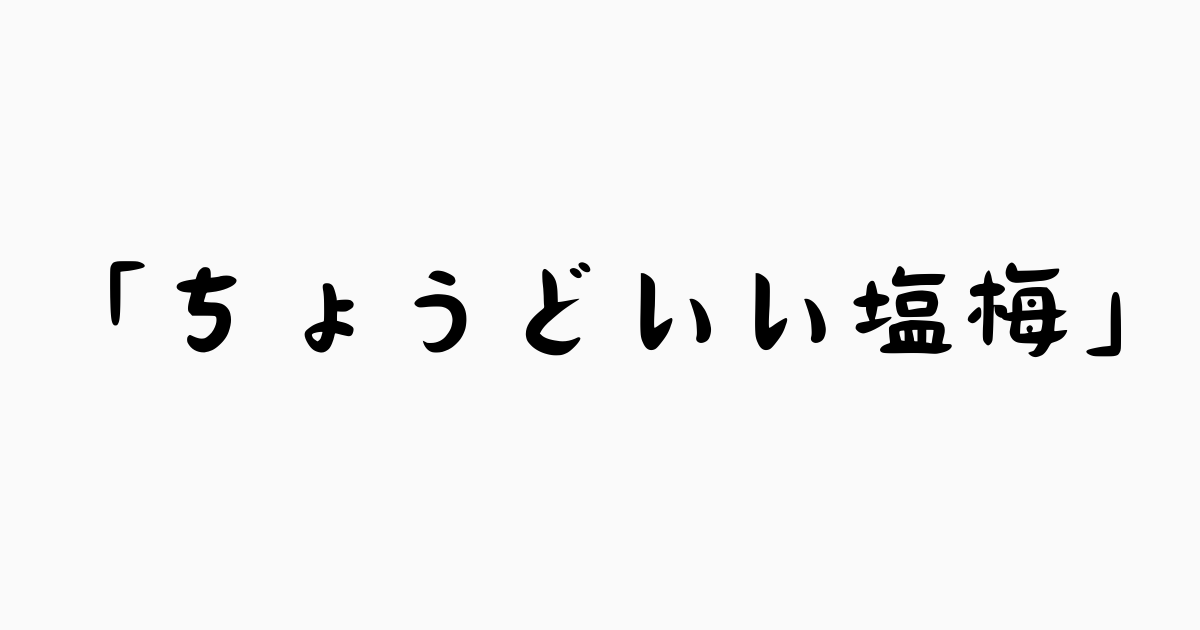
「ちょうど」とは「ある物事が過不足なく一致し期待・目的にうまく合うさま」「そのときまさに行われているさま」「そっくりそのままある物事にたとえられるさま」を意味し「ちょうどいい」とはこれらが適切である状態を言います。
「塩梅」は上述の通り、料理の味加減や物事の具合・調子・加減、からだの具合を意味します。
すなわち「ちょうどいい塩梅」とは物事のバランスや調整が、期待・目的と一致している状態を言います。
「シンプルさのなかに華やかさもあってちょうどいい塩梅だね」
「この天気なら散歩にちょうどいい塩梅だ」
などのように使われます。
「ちょうどいい塩梅」の類義語には「絶妙なバランス」「程よい加減」や「ちょうどいい具合」があり、自分の目的などに対して、期待通りにできたことを表現する際に使われます。
参考文献
- 編 松村明・三省堂編修所(2019)『大辞林』第四版.三省堂.
- 編著 北原保雄 (2010)『明鏡国語辞典』第二版, 大修館書店.
- 小学館.「デジタル大辞泉」. <https://dictionary.goo.ne.jp/jn/>(参照日2024年12月3日).
- 公益財団法人日本漢字能力検定協会.「漢字ペディア」.<https://www.kanjipedia.jp/>(参照日2024年12月3日).