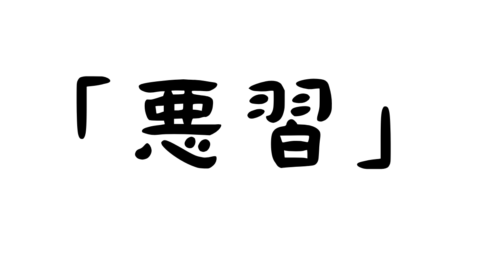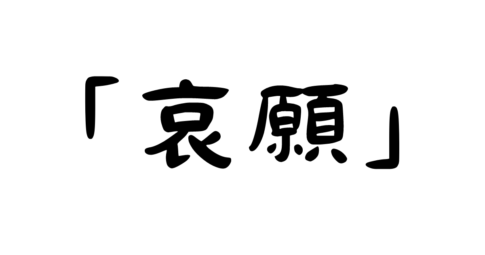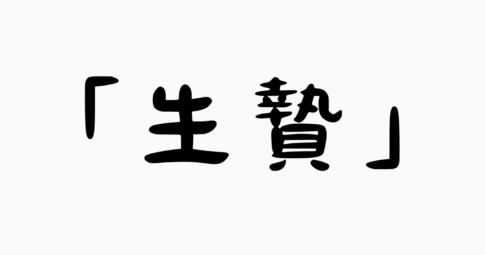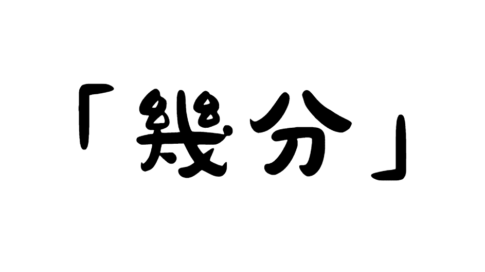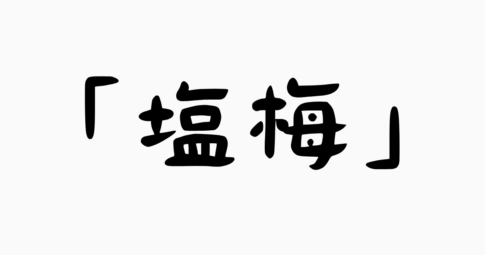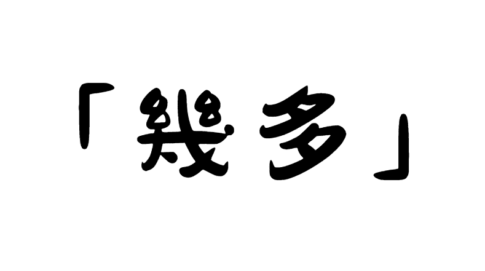「安堵」とは?意味・読み方や類義語・対義語は?
「安堵」は「あんど」と読み、「気がかりなことが解消されて、ほっとすること」を意味しています。
また、「安堵」の言葉の由来となっている「垣根の内側で安心して暮らすこと」や、時代によって使われた「幕府などが土地の所有権などを認めること」の意味もあります。
- 近隣で多発していた事件の犯人が捕まり、住民からは安堵の声が上がった。
- 行方不明になっていた犬が突然目の前に現れ、驚きと共に、安堵のため息をついた。
- 手術が上手くいったと聞き、安堵の表情を浮かべた。
- 江戸時代に入ってからも江戸幕府から所領を安堵されるなど保護された。
などのように使われます。
「安堵」は中国の歴史を記した「史記」の田單(でんたん)列伝の一節、「堵に安んず(とにやすんず)」が語源と言われています。
「堵」は「土で固めた垣(かき)、垣根、それらに囲まれた居所など」の意味で、「堵に安んず」は、「垣のうちで心やすらかにいること、居所に安住すること」を指す漢語表現として、日本でも用いられていました。
平安後期以降の封建時代に入ると、「安堵」は土地の私有制と深くかかわる言葉になりました。
所有権争いをしている土地の領有権を保護することで所有者を「安堵」させるというところから、幕府による公的な承認そのものを「安堵」と言うようになりました。
また、領有権を保証する内容が書かれた公文書を、「安堵状」と呼び、明治維新後の武家の解体まで続きます。
これらのことから中世以降、土地を守ることや封建制度における主従関係の維持のために、「安堵」が果たした役割は大きなものだったと考えられます。
そして、明治以降は、安堵の意味合いが精神面の安らかさに重きを置くように変わっていき、「不安や心配事が解消されて安心すること、気がかりなことがなくなってほっとすること」の意味が一般的となりました。
「安堵」の類義語には、「安心」「人心地」「胸をなでおろす」などがあります。
「安堵」の対義語・反対語には、「危惧」「憂慮」「心配」などがあります。
「安堵」の使い方




「安堵」の例文
- ・・・、やむを得ず狂暴性患者房に閉じ込めるしか方法がなかったそうだ」 タイラーは大きな安堵を覚えた。 「それは気の毒にな」 「とにかく、きみの家族にとっても、彼女はもう何
- ・・・昭和十九年からは、兵役が早められて十七歳)で死を義務づけられた時代から解放された安堵と、生命の自由を感じた。それこそ当時の私にとって「本当の自由」であった。であるか
- ・・・ニコロから受け取り、決められた箇所に署名した。そしてニコロに書類を返すと同時に、安堵感に包まれた。ここ数カ月間で初めて、自分が正しい判断を下したと確信できた。ニコロ・・・Porter Jane.(著)/ 夏木 さやか(訳)「孤独を抱きしめて」
- ・・・動くのをやめてしまったかのようだ。やっと扉が左右に開く。並み居る人の胸からほっと安堵の息がもれる。いよいよお祭りだ。オーケストラの指揮者が手をふりあげる。だがプラト・・・アンリ・トロワイヤ(著)/ 工藤 庸子(訳)「女帝エカテリーナ」
「安堵」「安心」の違いは?

「安堵」「安心」のそれぞれの違いを見ていきましょう。
「安堵」と「安心」は、「気がかりがなく心が落ち着く」という意味の類義語です。
「安堵」は「気がかりなことが解消されて、ほっとすること」で、危険や心配事が解消した後に起こる一過性の喜びや安らぎの感情を指します。
「安心」は「心配や不安がなくて心が安らかなこと、気がかりなことがなく、心が落ち着いていること」で、何事もなく平穏な心の状態が続いていることを指しています。
もともと「安心」は儒教の「安心立命」という「心を安らかにし身を天命に任せ、どんな場合にも動じない」という教えで、仏教でも「信仰により心をひとつにとどめて動かないこと」、平たくいえば、「安定している心」を指す言葉です。
「安堵」と「安心」はよく似ていますが、「安堵」には「不安な事、気がかりな事」などの前提があり、それらがクリアされたことでほっとするというニュアンスが強くあります。
つまり、「安堵」は先に緊張状態があり、そこから解放される、という流れがあってこそ体感する感情です。
「安心」は、仏教用語と言うこともありますが、重要なのは心が安定している状態でいることで、実際には不安や恐怖があろうと、心の中ではそれを気にかけず、落ち着いていることを指します。
例えば、大雨の夜、一人で居るときは心細く不安を強く感じますが、友人が来てくれると、現実の大雨やその心配は変わっていないのに、「安心」する、ということもあります。
このように「安心」は心が落ち着いていることを言い、人やものごとに使われることもあれば、状況や場所などに対して使われることもあります。
そして、類義語の「安堵」と「安心」は、「安堵」の「堵」という文字が常用漢字表の表外字であることから、言い換えとして「安心」を使うことが多くあります。
しかし、「安心」を用いた言い回しのすべてを「安堵」に置き換えることはできないため、言い換えには注意しましょう。
例えば、「ひとまず安堵した」は「安心」に置き換えられますが、「安心して治療を受けてください」は「安堵」に置き換えられません。
これは、「安堵する」には「心配がなくなる」という意味しかありませんが、「安心する」には「心配がなくなる」という意味の他にも「心配がない状態が続く」という意味も含まれるからです。
「安心」の例
- ・・・漬けるのに使っていた容量9ℓほどのふたのない筒状のかめを愛用しています。 さらに安心して飲むために、このかめの水を沸騰させます。鉄びんのふたをとって火にかけ、換気を・・・髙橋 蕙子(著)「地球と生きる133の方法」
- ・・・丈夫ですわ。あと一刻も眠ったら、口がきけるようになりましょうかい。ああ、これで一安心や」 しかし於継は応えなかった。彼女は息子の口のまわりがどっぷりと黒豆の煮汁で染・・・有吉 佐和子(著)「華岡青洲の妻」
- ・・・ムを鑑賞する時にだけようやく無理をしない自分と向き合えたのです。過去のものは僕を安心させました。過去のものは、決して自分を裏切らない。現在進行形のものはそれに想いを・・・嶽本 野ばら(著)「カフェー小品集」
「安堵」「安心」の違いまとめ
- 「安堵」「安心」は、「気がかりがなく心が落ち着く」という意味で、類義語です。
- 「安堵」は、「危険や心配事が解消して、緊張が解けてほっとする一時的な感情のこと」を指します。
- 「安心」は、「心配事がなく、精神的に落ち着いた状態が続いていること」を指します。
「安堵の気持ち」とは?

「安堵の気持ち」は、基本的にその前まで何か不安なことや心配事があり、それが解決した時の心理を表す言葉です。
つまり、「それまでの緊張や不安が解消されることで生じる、心の安らぎやほっとした感情」のことを指します。
具体的には、危機から脱したときやプレッシャーから解放されたとき、あるいは結果が予想以上に成功したときなどの後、一時的に感じる心の安らぎや喜びの感情です。
そしてこの「安堵の気持ち」は、緊張から解放されることで心身がリラックスし、心穏やかになっていることが特徴です。
例えば、「10年以上の介護を終えることができた時は、悲しみ・寂しさと同時に安堵の気持ちもありました。」というのは、介護対象との別れの寂しさはあるけれど、介護の心配が終わりやっと落ち着ける…など、複雑な思いが伝わります。
また、「前理事長は会見を開き、改革の道筋がついたので新理事長にバトンを渡す。若干、安堵の気持ちもある、と語った。」というのは、自己の実績評価をして悔いの残るところもあるが、退任することで肩の荷をおろせた解放感もある、という気持ちでしょう。
参考文献
- 編 山田忠雄・柴田武・酒井憲二・倉持保男・上野善道・山田明雄・井島正博・笹原宏之 (2012)『新明解国語辞典』第七版, 三省堂.
- 監 林 四郎 編 篠崎 晃一 ・相澤 正夫・大島 資生(2021)『例解新国語辞典』第十版, 三省堂.
- 編 柴田武・山田進 (2002)『類語大辞典』講談社.
- 編 藤堂明保・松本昭・竹田晃・加納喜光 (2011)『漢字源』改訂第五版, 学研.
- 著 鎌田正・米山寅太郎(2013)『新漢語林』第二版, 大修館.
- 編 松村明・三省堂編修所(2019)『大辞林』第四版.三省堂.
- 公益財団法人日本漢字能力検定協会.「漢字ペディア」.<https://www.kanjipedia.jp/>(参照日2024年12月1日).
- 小学館.「デジタル大辞泉」. <https://dictionary.goo.ne.jp/jn/>(参照日2024年12月1日).


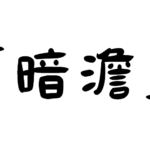

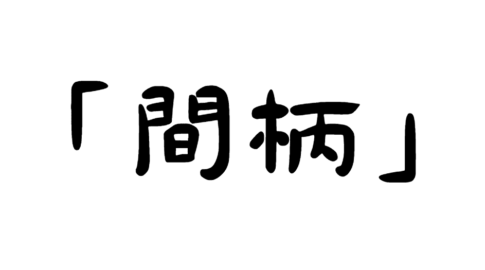
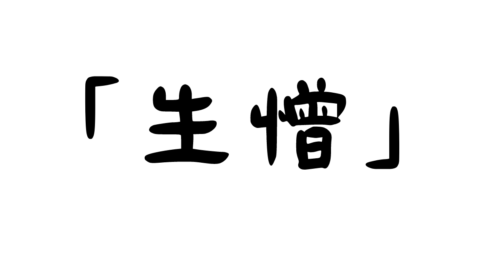
-485x255.png)