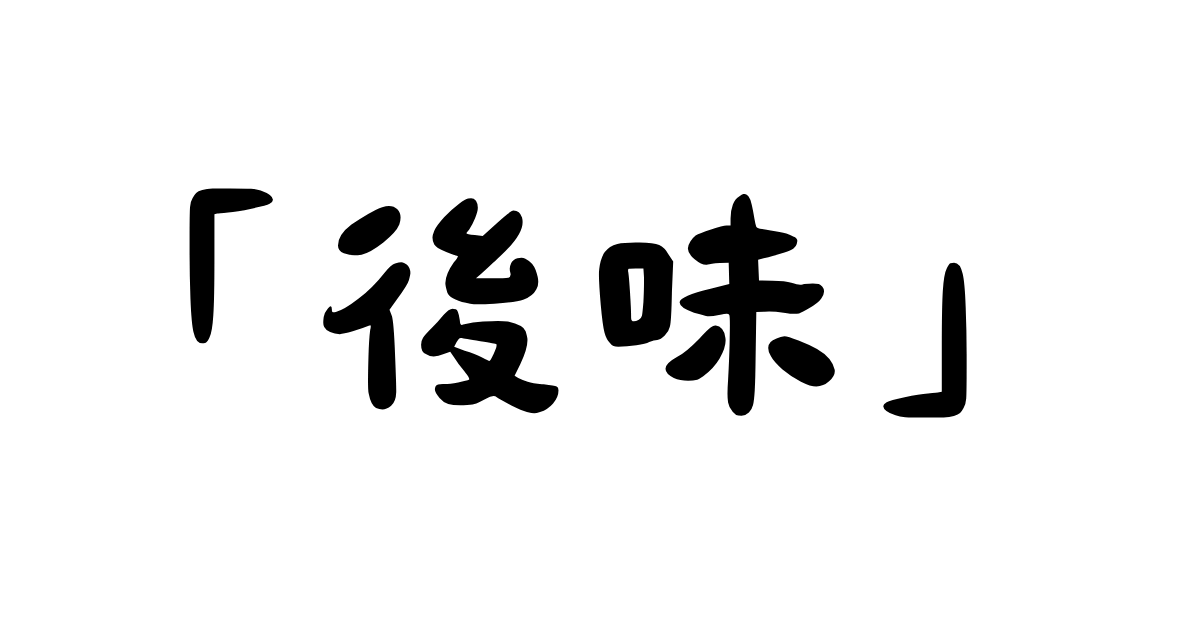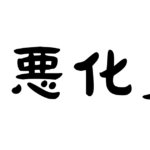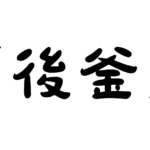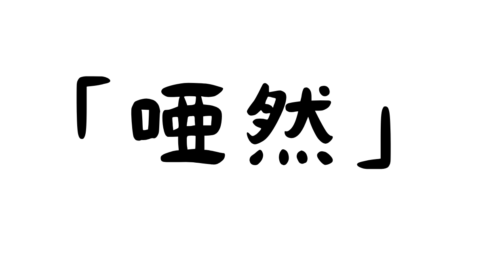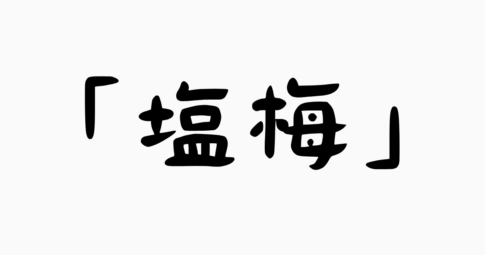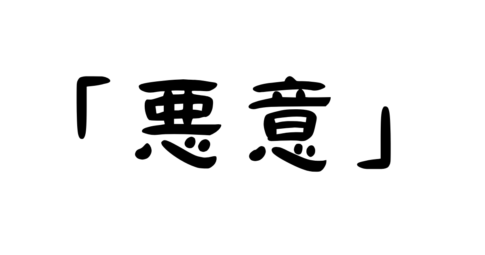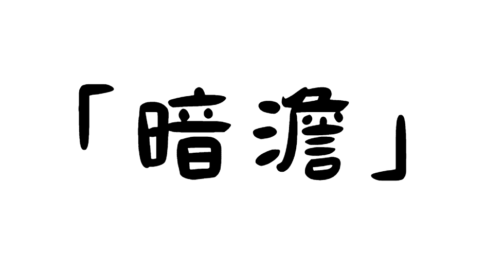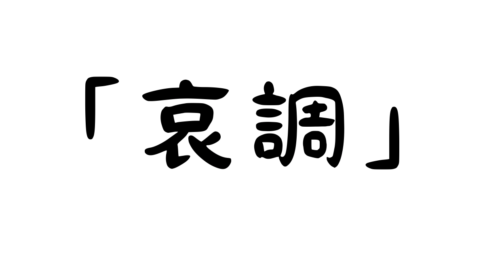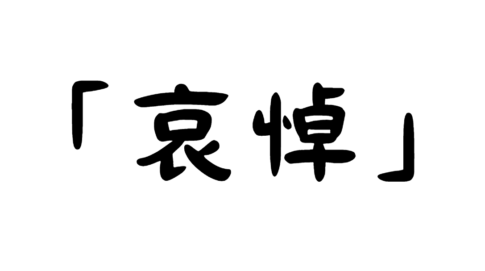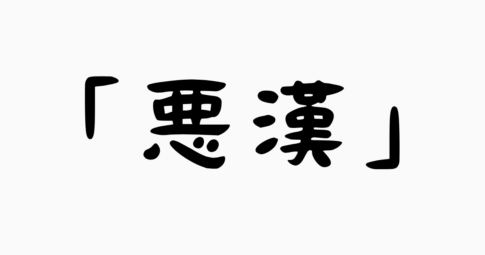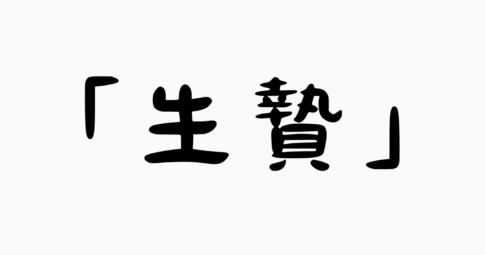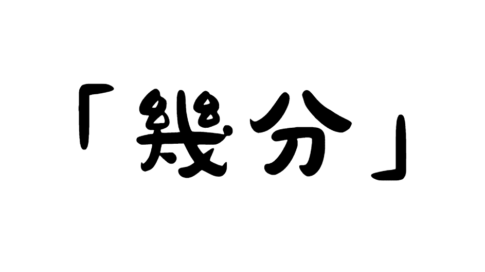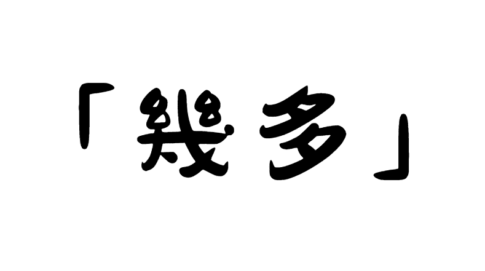「後味」とは
「後味(あとあじ)」とは、「食べたり飲んだりした後に口の中で残る味わい」を表す言葉ですが、終わった後に残る様子から転じて「物事が済んだ後に残る感じや気分」という意味もあります。
- やさしい甘みと上品な後味が特徴の煎茶。
- そのウイスキーは、特有のスモーキーな後味が口の中に残る。
- 不快な後味が残る映画で、がっかりした。
- 彼女の言葉は、いつもさわやかで心地よい後味を残す。
などのように使われます。
「後味」とは、食べ物や飲み物の味わいに関する言葉で、「口の中に残る味わい」を指します。飲食を楽しんだ後に感じる味わいは、私たちの食事を豊かにします。
例えば、甘いデザートを食べた後に残るわずかな塩味、コーヒーの苦味の後に残るすっきり感などが「後味」として感じられるとき、この「後味」は、味覚だけでなく香りや風味も含まれ、飲食の楽しみを深める重要な要素になります。
そして、食卓を囲む家族の会話やお店の雰囲気や接客態度なども「後味」を左右する要素になり得ます。
良い「後味」は「食べたものの満足感」を高め、逆に悪い「後味」は食事の楽しみを損ね、「二度と食べたくない。二度と来店しない」となることもあります。
食に関する「後味」の類義語には、「後口(あとくち)」があります。
ところで、「後味」に対して、食前の雰囲気や口に入れた瞬間の味を指して「先味(さきあじ)」を対義語として使うことがありますが、この「先味」は造語です。
また、「後味」には、上述のように終わった後に残る様子から転じて、「物事が済んだ後に残る感じや気分」という意味があり、食に限らず、様々なシーンで使うことができます。
例えば、映画を見終えた後に「どんな印象が残ったか」を、食べ物や飲み物の「後味」になぞらえて表現します。
「その場で終わらずに後まで残る」気分を強調するために、比喩的に「後味の悪い映画」などといった表現で用います。
このような、後に残る気分を指す場合の「後味」の類義語には、「後口」「名残」「余韻」「余情」などがあります。
「後味」の使い方




「後味」の例文
- ・・・リステリンで歯をすすぐ。ようやく、口中にかすかに残っていたアルコールの後味がさっぱりした。
- ・・・その説にしたがえば、闇市のシルコの甘さはズルチンということになる。どちらも、舌に厭な後味が残るのだが、そのくらいは何程のこともなかった。
- ・・・には片思いだということがわかっているのだから。長谷川さんへの取材はなぜかとても後味がよかった。それは彼の人間性からくるところが大きいのだろう。お金も大事、名誉も・・・亀山 早苗(著)「夫が職を失ったとき」
- ・・・ゴールインしてしまっている。最終作『佐原の血煙り後家』などは計算ちがいの材料で、後味のよくない結末になっている、が、逃口上がないわけでもない。 現在通用する滑稽の意・・・八剣 浩太郎(著)「大江戸浮世草紙」
「後味が悪い」とは?
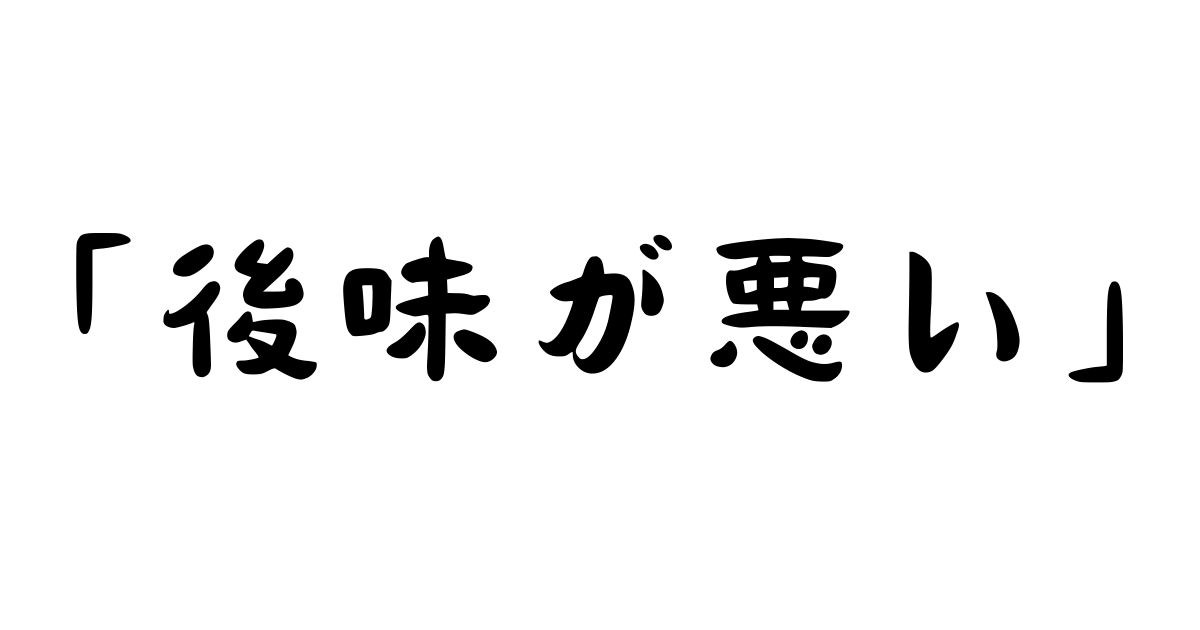
「後味が悪い」は慣用句で、「物事が済んだ後もすっきりしない嫌な気分が残り、不快な感じ」を意味します。
物事が終了してもその場で終わりにならず後まで不快感が残っていることを強調しています。
「後味が悪い」の類義語には、「腑に落ちない」「合点がいかない」「割り切れない」といった「終わった物事に対して悪い印象がある、結果に対して受け入れがたい」という意味を持つ言葉があります。
ただし、「後味が悪い」は、「納得いかない」というよりは「そんなことがあって残念だ」というニュアンスになり、自分の行動だけではなく、ある事柄に対する客観的な感想としても使われる表現です。
参考文献
- 編 山田忠雄・柴田武・酒井憲二・倉持保男・上野善道・山田明雄・井島正博・笹原宏之 (2012)『新明解国語辞典』第七版, 三省堂.
- 監 林 四郎 編 篠崎 晃一 ・相澤 正夫・大島 資生(2021)『例解新国語辞典』第十版, 三省堂.
- 編 柴田武・山田進 (2002)『類語大辞典』講談社.
- 編 藤堂明保・松本昭・竹田晃・加納喜光 (2011)『漢字源』改訂第五版, 学研.
- 著 鎌田正・米山寅太郎(2013)『新漢語林』第二版, 大修館.
- 編 松村明・三省堂編修所(2019)『大辞林』第四版.三省堂.
- 公益財団法人日本漢字能力検定協会.「漢字ペディア」.<https://www.kanjipedia.jp/>(参照日2024年10月25日).
- 小学館.「デジタル大辞泉」. <https://dictionary.goo.ne.jp/jn/>(参照日2024年10月25日).